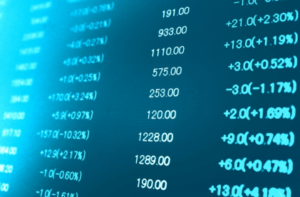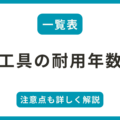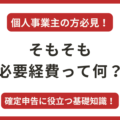こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
中小企業の経営者の方から、余剰資金を用いた株式投資や投資信託への投資を「法人で行う場合と個人で行う場合どちらが節税できるのか」とのご質問いただくことが増えてきました。
法人で株式投資や投資信託への投資を行うことで節税することができないか‥
株式投資にもいろいろありますが、証券会社を通して上場会社の株式投資や投資信託の購入を法人口座で行うのか、個人口座で行うのかについてのご質問です。
個人と法人では、同じ株式投資の利益の金額でもかかる税金が大きく異なってくるケースがあります。
これから株式投資を新たにスタートする想定すると、
法人に多額の欠損金があり、かつ、欠損金の範囲内の株式投資の利益を見込む場合には、法人の方が節税することができ、
それ以外の場合は、特に法人で800万の利益がでている場合には、個人の方が節税ができるケースが多いと考えています。
株式投資や投資信託の利益に対する課税は、法人は、他の事業の赤字や色んな経費と相殺することができたり、過去の赤字の繰越期間10年と長いことメリットがありますが、個人は最大約14%の税率が低いメリットがあるからです。
個人の方が節税できるというのは、あくまで一般的な場合で、それぞれのケースによっては、どちらが有利になるかは異なります。
以下では、ケースで株式投資や投資信託への投資を個人と法人のどちらで行うかを決める際に、参考となる税金の取扱いの違いや銀行対策など法人と個人のメリット、デメリットについて説明したいと思います。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
税理士法人Accompanyでは、法人での株式投資に関してのご相談を承っております。
「株式投資を個人・法人どちらで取り組むか悩んでいる」という方は、無料シミュレーションを行っていますので、ぜひお問い合わせください。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
\24時間365日受付中 /
株式投資に対する法人と個人の税率や赤字の相殺期間の違い
上場会社の株式投資や投資信託への投資の利益に対する税率と赤字の相殺期間など個人、法人の税務上の取扱いの違いは以下の表のようになっています。
| 個人と法人の税務の違い | 個人 | 法人 | |
| 税率 | 年間所得(利益)金額が400万以下 | 一律20.21% | 21.7%(資本金1000万以下の場合) |
| 400万超800万以下 | 23.5%(資本金1000万以下の場合) | ||
| 800万超1000万以下 | 34%(資本金1000万以下の場合) | ||
| 赤字の相殺期間 | 3年 | 10年 | |
| 経費にできる範囲 | 利息のみ | 株式投資を含む事業にかかる経費 | |
| 非課税枠 | 年間360万 生涯1800万 | なし | |
課税される利益は、売却し確定した利益に対して課税され、含み益に課税されませんのでご注意ください。
株式投資の目的は、通常より多くの利益を得ることだと思います。
株式投資の利益は次のように計算されます。
同じ税引前の投資利益でも税金の金額が変わると、最終的な株式投資の利益は変わるので、、株式投資の利益に対する税金額を抑えることができれば、投資効果をより高めることができます。
よって、ここからどのようにすれば株式投資の投資効果を税金面から最大にできるかについて解説していきたいと思います。
株式投資の個人の税率
個人は、どんなに多額の利益がでても株式投資の利益に対する税率は、一律20.21%です。
役員報酬やその他不動産などの収入とは切り離し、いわゆる分離課税という方式で課税されます。
20.21%には国と都道府県、市区町村全ての税率を含ます。
株式投資の法人の税率
一方、法人の税率は、年間の株式投資を含むすべて利益合計が
- 利益が400万以下に対する税率:21.7%
- 利益が400万超800万以下に対する税率:23.5%
- 利益が800万超に対する税率:34%
となっています。
以上のように法人の場合、利益の金額によって税率が大きく異なります。
法人の場合には、トータルの年間利益が800万を超えると、超えた金額に対する税率が34%となり、税率が高くなります。

よって、年間の利益が800万を多額に超えるかどうかが、税負担が大きくなるの境目となります。
個人と法人の赤字と他の所得との相殺方法の違い
上場会社の株式投資や投資信託への投資から赤字が生じた場合、その赤字は、個人の場合は、3年間の繰り越しとなり、法人の場合には10年間の繰り越しが可能です。
繰越すことによって、次年度以降に生じた利益と相殺して、税金を計算することが可能です。
例えば、ある年に50万円の赤字が生じ、次年度に200万円の利益が生じたときの税金計算のベースとなる利益は、200万円から50万円を控除した150万円となります。
この点を考えると、過去に多額の赤字があり、利益が多額になるな視点で株式投資を行う場合には、法人の方が良い可能性もあります。
また、株式投資から生じた赤字は、個人の場合、配当以外の利益と相殺することができません。
しかし、法人の場合には、本業に係る利益と相殺することができます。
NISA制度を活用し個人で節税
株式投資の非課税制度であるNISA制度を使えば、個人側で節税が可能です。
法人ではNISA制度はありません。
よって、個人では、成長投資枠で年間240万、積立投資枠で年間120万の合計年間360万、生涯1800万の投資枠を非課税にすることができます。
この非課税枠の範囲内であれば、株式投資や投資信託に対する税金はかかりません。
株式投資の税率差の違いによる税負担の違い
ここでは具体例で考えてみます。
仮に株式投資から3,000万の利益がでている場合で、NISAの非課税枠を300万使えたとすると、
個人で株式投資を行う場合、546万円の税負担となり、税引き後の最終的な利益は、約2,454万円となります。
法人で株式投資を行う場合、過去の赤字と他の事業の赤字の合計が3000万以上ある場合には、税負担はゼロ、税引き後の最終的な利益は3,000万となり、個人より546万円株式投資の利益が多くなります。
ただし、利益の合計が800万超となっている場合に、株式投資の利益が上乗せされると1,020万の税負担となり、税引き後の最終的な利益は1,980万円となり、個人よりも474万円株式投資の利益が小さくなります。
このように法人の場合、赤字の有無によって、最大1020万の税金負担の違いがあるので、過去の赤字の金額、今後の本業の事業計画を作成し、利益をシュミレーションする必要があります。
法人から個人へ貸付を行う場合の注意点
法人の資金を使って個人で株式投資を行う場合に注意点があります。
一つは、役員賞与とみなされないように、あくまで一時的な貸付であること客観的に証拠を残し、法人と役員間で契約書を作成した方が安全です。
金融機関からの残高が大きく、その融資金額を個人への貸付に回してしまうと、金融機関からの評価は良くないので、自社の資金で行う方が金融機関との関係を維持することができます。
あと、税務上で役員への貸付金となってしまうため、個人から利息を受け取る必要があるので、法人側で認定利息に対する課税が生じてしまいます。
株式投資を行う場合の認定利息が個人で経費にできる
ただし、役員が法人から借入を行い、その資金を持って株式投資を行う場合の認定利息については、個人側で必要経費にすることができるので、個人の税負担を少なくすることができます。
よって、認定利息が多額ならない限りは、個人側での負担は気にしなくて良いと考えています。
個人と法人の株式投資を節税メリットの違いのまとめ
以上のように法人、個人と株式投資を行う場合の税金上の取り扱いは大きく異なります。
決め手となるのは以下の2点です。
- 法人に欠損金があり、このまま期限切れになる可能性がある
- 多額に株式投資を行い、法人側で年800万を超えて利益がでる見込みがある
1の場合には、過去の赤字を活用できるため、法人で株式投資を行う方が節税できる可能性があります。
2の場合には、個人の方が税率約14%低くでき、節税できる可能性があります。
株式投資の難しいところは、本業の利益よりも利益が読めないところだと思います。
株式投資が少額になる場合には、個人と法人の違いにより、税負担は大きく変わりませんが、
株式投資が多額になる場合には、税負担が大きく変わる場合があるので事前のシミュレーションをしっかり行い、個人か法人かを決められてください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
税理士法人Accompanyでは、法人での株式投資に関してのご相談を承っております。
「株式投資を個人・法人どちらで取り組むか悩んでいる」という方は、無料シミュレーションを行っていますので、ぜひお問い合わせください。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
\24時間365日受付中 /

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。