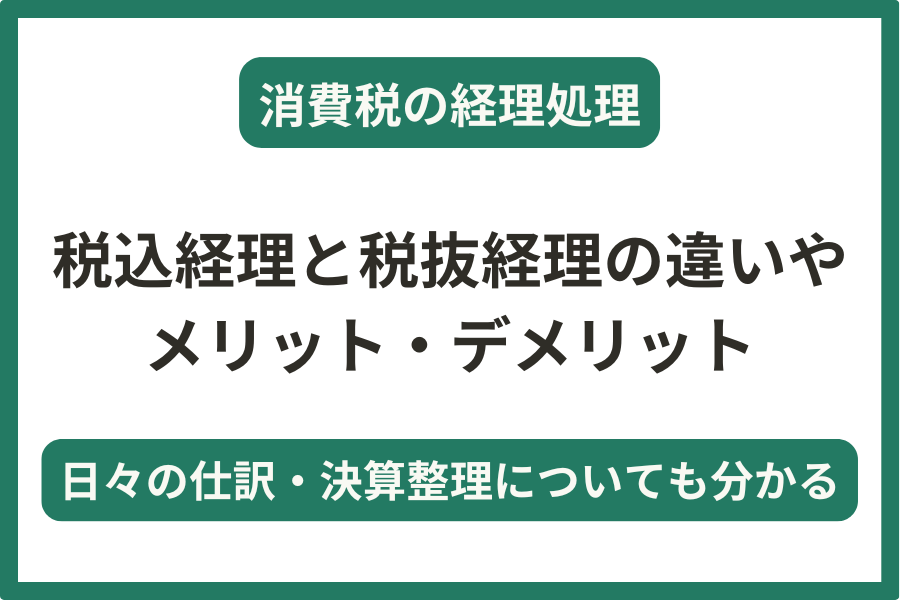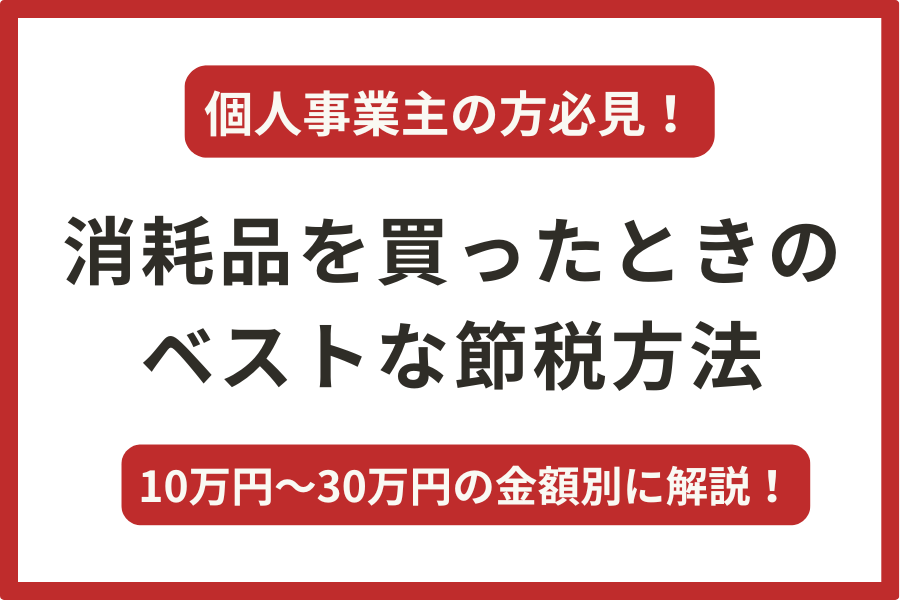こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
弊社のブログをご覧の方の中にはご自身で記帳を行っている方もいらっしゃるのではないかと思います。
今回は、消費税の経理処理を「税込経理方式」と「税抜経理方式」どちらにすべきかということについて解説した記事になっています。
- 2つの経理処理はそれぞれどう違うのか知りたい
- 今まで免税事業者だったから気にしていなかったが、消費税を納めるようになるので検討したい
- それぞれのメリットやデメリットを知りたい
- 具体的な仕訳の仕方を知りたい
というお悩みを抱える経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、本記事では
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- 交際費の上限
について触れていますので、上記に当てはまる中小企業の経営者または経理担当者の方を対象にした記事である点についてご留意ください。
この記事で分かること
中小企業の経営者・経理担当者が…
- 税込経理方式と税抜経理方式の違いが分かる
- 仕訳処理の違いが分かる
- 決算時(確定申告時)の消費税の仕訳の仕方が分かる
- それぞれのメリットとデメリットが分かる
- 税込経理でも消費税の納税額を予測する方法が分かる
- 消費税の納税額を加味した損益を把握する方法が分かる
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
弊社では、決算や確定申告までに消費税の予測納付額をお伝えしています。
お客様のご要望に応じて税込経理でも税抜経理でも記帳が可能で、
「決算ギリギリ・確定申告ギリギリまでいくら払うことになるのか分からず不安」
という方のために会計に消費税の納付額を反映させることも可能です。
また、初回のご面談は無料で記帳代行や毎月の顧問契約についてのご相談をしていただくこともできます。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
まずはお気軽に問い合わせください。
\24時間365日受付中 /
『会計税務顧問サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。
目次
税込経理方式と税抜経理方式の違いとは?
税込・税抜経理方式とは、消費税の会計処理方法に関する2つの異なる方式のことです。
分かりやすく言うと、消費税が含まれる取引を会計に入力する際に
- 取引金額に消費税を含めた金額で会計処理を行うのが税込経理
- 取引金額に消費税を含めずに、別で消費税を入力するのが税抜経理
となっています。
税込経理方式とは
税込経理方式とは、取引金額に消費税を含めた金額で会計処理を行う方法のことを言います。
つまり、消費税を経費や収益と一緒にまとめて処理するのです。
例えば
- 110円(税込)で消耗品を買ったとき
- 11,000円(税込)の売上が上がったとき
税込経理方式の場合は下記のように仕訳をします。
税込経理の例
110円(税込)で消耗品を購入した場合
| 消耗品費 | 110円 | 現金預金 | 110円 |
11,000円(税込)の売上が上がった場合
| 現金預金 | 11,000円 | 売上高 | 11,000円 |
税抜経理方式とは

続いて税抜経理方式について解説していきます。
税抜経理方式とは、取引金額から消費税を分けて仕訳をする会計方式のことです。
消費税は収益や費用には含めず、「仮払消費税」「仮受消費税」という勘定科目を使います。
税抜経理方式の場合は下記のように仕訳をします。
税抜経理の例
110円(税込)で消耗品を購入した場合
| 消耗品費 | 100円 | 現金預金 | 110円 |
| 仮払消費税 | 10円 |
11,000円(税込)の売上が上がった場合
| 現金預金 | 11,000円 | 売上高 | 10,000円 |
| 仮受消費税 | 1,000円 |

税込経理と税抜経理の違いは仕訳にしてみると分かりやすいのではないでしょうか?
この経理処理方法については税抜経理と税込経理のどちらを選択してもよいこととされていますが、
免税事業者(消費税を納める義務がない事業者)については税込処理で会計入力をする決まりになっています。
免税事業者には消費税を計算する必要が必要ないため、消費税を分けて記帳をする税抜経理が選択できないということです。
また、選択した方式は、その事業者が行うすべての取引に適用するのが原則となっています。
そのため、例えば一部の売上は税抜経理、一部の仕入は税込経理にするなど、自社にとって都合の良いように操作することはできません。

ちなみにどちらの方式を選択しても、納付する消費税等の金額は同額となります。
次は、決算(確定申告)の時、消費税の計算が終わった後の仕訳方法について解説します。
決算(確定申告)の時の消費税の仕訳はどうやるのか?
会計ソフトを使用している場合は、日々の取引を仕訳するときに消費税の区分を選択します。
先ほどの例を元に解説すると…
| 勘定科目 | 取引金額 | 税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 110円 | 課税仕入10% |
| 売上高 | 11,000円 | 課税売上10% |
このように入力していくことで、会計ソフト上で自動的に
- 1年間を通してそれぞれの税区分の消費税がいくらあったか
が分かります。
そして、消費税の計算方法はさまざまですが、計算が終わると消費税の納税額が分かります。
※消費税の計算方法については別の記事で詳しく解説させていただく予定です
ここで説明するのは、消費税の計算が終わった後の会計への入力方法です。
早速ですが、
消費税の納税額を10,000円とした場合の仕訳方法を解説していきます。
税込経理の場合の消費税の決算整理仕訳
消費税の納税額:10,000円
| 租税公課 | 10,000円 | 未払消費税 | 10,000円 |
この「租税公課」という勘定科目は損益計算書(P/L)の科目ですので、
- 個人事業主なら経費
- 法人なら販管費及び一般管理費
となるため、消費税の仕訳を入れた後は損益が変わります。
そのため、消費税の計算をするのは全ての会計入力が終わった後、法人税申告書(確定申告書)を作成する前にしましょう。
続いて、税抜経理の場合の消費税の決算整理仕訳の仕方を解説していきます。
期中は
- お金が出ていくたびに借方(左側)に仮払消費税
- お金が入ってくるたびに貸方(右側)に仮受消費税
が溜まっていきます。
決算整理では、それぞれを逆仕訳(相殺)してゼロにするとともに、差額を未払消費税とします。
税抜経理の場合の消費税の決算整理仕訳
消費税の納税額:10,000円
| 仮受消費税 | 90,000円 | 仮払消費税 | 80,000円 |
| 未払消費税 | 10,000円 |

この仕訳を入れた後は、「仮払消費税」と「仮受消費税」がきちんとゼロになっているかどうか、貸借対照表をチェックしましょう!
上記の仕訳を入れた後に数百円の端数が出てしまった場合ですが、
これは「消費税差額」と呼ばれるもので、消費税の計算過程で生じた端数です。
※この差額について詳しく解説した記事を本記事とは別に執筆中です。
この消費税差額は消費税の計算方法(原則・簡易課税・2割特例など)によって生じる金額が変わってきます。
消費税の計算方法や消費税の差額については改めて別の記事で詳しく解説したいと思います。
消費税差額が出た場合の仕訳方法
差額が借方(左)に出た場合
| 仮受消費税 | 90,000円 | 仮払消費税 | 80,000円 |
| 雑損失(消費税差額) | 100円 | ||
| 未払消費税 | 10,000円 |
※雑損失の消費税区分は「対象外」
差額が貸方(右)に出た場合
| 仮受消費税 | 90,000円 | 仮払消費税 | 80,000円 |
| 雑収入(消費税差額) | 100円 | ||
| 未払消費税 | 10,000円 |
※雑収入の消費税区分は「対象外」
消費税の計算さえ終わってしまえば仕訳の入力は簡単です!
次は税込経理と税抜経理のメリットとデメリットを説明します。
税込経理と税抜経理のメリットとデメリットは?
先ほど解説したように、免税事業者の間は税込経理で会計入力をしますので、
何もしなければそのまま税込経理で会計処理をすることになります。
それでは、
- 何もせずに税込経理のままでいいのか?
- わざわざ税抜経理に変更するメリットはあるのか?
と気になった方もおられると思います。
この章では、税込経理と税抜経理のメリットとデメリットをまとめています。
早速結論ですが、税込経理と税抜経理のメリットとデメリットをまとめると下記のようになります。
税込経理のメリット・デメリット
【メリット】
- 記帳方法が簡潔
- 固定資産の管理が容易
- 免税事業者の頃と売上や経費を比較する時に会計が見やすい
【デメリット】
- 期末まで消費税の納税額が分からない
- 費用や収益に消費税が混ざっているため、実態が見えにくい
- 建設業で「経審」をする場合は税込の試算表を税抜に組み替える必要がある
次は、税抜経理のメリットとデメリットについてまとめました。
税抜経理のメリット・デメリット
【メリット】
- 消費税の納税額を把握しやすい
- 消費税率が改定されても影響が出にくい
- 固定資産の購入時に有利
- 交際費が多い事業者は上限が上がる(法人の区分による)
- 建設業で「経審」をする場合でも試算表をそのまま使える
【デメリット】
- 処理の煩雑さ
- 帳簿と自身の感覚の間にズレが生じる可能性がある
それではそれぞれのメリット・デメリットについて、詳しく解説していきたいと思います。
税込経理のメリット①:記帳が簡単
税込経理のメリットとしてまず挙げられるのが、記帳の簡単さです。
税込経理の場合は領収書や請求書に載っている税込金額をそのまま会計ソフトに入力し、勘定科目を選択するだけで仕訳が完了します。
そのため本体価格と消費税額を分けて複数行取引で登録する必要がない(一行で仕訳が終わる)ため、処理方法が簡潔です。
税込経理のメリット②:固定資産の管理が容易
2つ目のメリットとしては固定資産の管理が簡単であるという点が挙げられます。
管理が簡単になる理由としては
- 固定資産台帳に登録するときに消費税を分けないので仕訳がシンプルになる
- 減価償却費の計算をする時は税込総額で行うため、償却費の計算が楽
というものがあります。
固定資産台帳に登録したり、決算整理仕訳の時に手間が少ない方がいい場合は税込経理がオススメです。
税込経理のメリット③:前期比較が見やすい
会計に入力した数字を確認する時の話なのですが、
損益計算書を前年と比較してみる「前期比較」という会計の見方があります。
これは
- 前期と比較して売上が上がったか、下がったか?
- 前期と比較して増減している経費はないか?
という情報を知ることができる会計の見方です。
会計は、
- 税込経理を選択していれば税込の金額
- 税抜経理を選択していれば税抜の金額
で表示されますので、免税事象者の頃と同じ税込経理を選択することで、前年と比較しても税込金額で収益や費用を比較することができ、会計が見やすいのではないかと思います。
ここまで税込経理のメリット3つについて解説しましたが、次はデメリットについて説明したいと思います。
税込経理のデメリット①:消費税の納税額が分からない
先ほど決算(確定申告)時の消費税の仕訳方法について解説しましたが、
消費税を計上する時の「租税公課」という勘定科目の金額は、消費税の計算が終わらないと分かりません。

税込経理では取引金額に消費税を含めて仕訳をしているので、損益計算書上のどこを見ても、消費税の納付額は載っていないのです。
そのため、決算や確定申告がくるまで、一体いくらの消費税を納めることになるのか分からず納税額の見通しが立ちづらいというデメリットがあります。
税込経理のデメリット②:収益や費用の実態が分かりづらい
ここで、消費税の基本的な部分について簡単に触れておきたいと思います。
まず、消費税とは、納税義務者(税金を納める義務がある人)と担税者(税金を負担する人)が異なる間接税と呼ばれる税金です。
消費税を納める義務がある人はモノやサービスを消費する消費者であり、
実際に消費税を支払う人は事業者となります。
そのため、事業者は消費者が負担すべき消費税を預かって、そのあと国に納めるという流れになっています。
つまり、消費税は「事業者にとっての収益や費用ではない」ということが言えます。
一時的に預かり最終的に国に納めるべき消費税が収益や費用に混ざっている状態のため、本業でどれだけ儲けたのか、どれだけ使ったのかが分かりづらくなります。
例えば、税込経理で11,000円(税込)の売上を会計に入力すると、
実際は10,000円の売上と1,000円の(一時的に預かっている)消費税であるにも関わらず、帳簿上は11,000円の収益として表示されてしまいます。
これにより、収益や費用の実態が分かりづらくなってしまいます。
税込経理のデメリット③:経審では試算表を税抜に組み替える必要がある
この経審とは「経営事項審査」の略で、建設業許可を受けた業者のうち、公共工事の入札に参加したい業者が受ける審査のことです。
経審における経営状況分析申請では、登録された分析機関に決算書などを提出し、数値を出してもらう必要があります。
この時に提出する資料は「税抜」表記の決算書などが必要になるため、「税込経理を選択している建設業の事業者が経審を受ける場合は資料を税抜表記に直す必要がある」ということになります。
会計には
- 消費税がかかるものとかからないものが混在
- 課税仕入10%・軽減税率8%・インボイス登録をしてない事業者への支払い(80%控除)などが混在
していることから、税込表記の会計資料を税抜表記に組み替えることは事業者にとっては難易度が高いと思われます。
そのため、
- 経審を毎年受ける
- 今後経審を受けたいと思っている
という事業者については税抜経理を選択した方がよいです。
税込経理のメリットとデメリットについて詳しく解説しましたが、次は税抜経理のメリットとデメリットの説明に移りたいと思います。

現時点では税込経理と税抜経理、どちらがいいかの判断はつきづらいと思いますので最後までご覧になってください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
弊社では、決算や確定申告までに消費税の予測納付額をお伝えしています。
お客様のご要望に応じて税込経理でも税抜経理でも記帳が可能で、
「消費税を納めるまでいくら払うことになるのか分からず不安」
という方のために会計に消費税の納付額を反映させることも可能です。
また、初回のご面談は無料で記帳代行や毎月の顧問契約についてのご相談をしていただくこともできます。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
まずはお気軽に問い合わせください。
\24時間365日受付中 /
『会計税務顧問サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。
税抜経理のメリット①:消費税の納税額を把握しやすい
まずは税抜経理のメリットひとつ目について解説していきます。
先ほどご説明したように、税抜経理では日々の取引のたびに「仮払消費税」と「仮受消費税」を分けて入力していきます。
その過程で貸借対照表に「仮払消費税」と「仮受消費税」が少しずつ積み上がっていきます。
決算整理仕訳のときのことを思い出していただきたいのですが、
税抜経理の場合の消費税の納付額は「仮受消費税と仮払消費税の差額」でした。
| 仮受消費税 | 90,000円 | 仮払消費税 | 80,000円 |
| 未払消費税 | 10,000円 |
ということは、貸借対照表を見て仮受消費税から仮払消費税を差し引けば、その時点での消費税の納付額が分かるということになります。
※取引登録の際に税区分が正しく選択されていることが前提となります。
そのため、決算(確定申告)を待たずに、期の途中で消費税のおおよその納付額を把握することが可能となります。
税抜経理のメリット②:消費税率の改定の影響を受けにくい
現在は消費税率は10%(軽減税率対象であれば8%)となっていますが、過去を振り返るとたびたび消費税の改定がありました。
| 消費税に関する出来事 | 改定時期 | 改定後消費税率 |
|---|---|---|
| 消費税導入 | 1989年 | 3% |
| 消費税率改定 | 1997年 | 5% |
| 消費税率改定 | 2014年 | 8% |
| 消費税率改定 | 2019年 | 10% |
| インボイス制度導入 | 2023年 | – |
これを見ると、数年単位で消費税率が徐々に上がっていることが分かります。
事業を長く継続していけば、今後も消費税率の改定がある可能性を否定できません。
しかし、仮に消費税率が改定されたとしても、税抜経理であればもともと税抜金額で会計の金額が表示されていることから、消費税率の変動によって数字が上下することはないのです。
そのため、過去の会計データを比較する時でも純粋な損益を把握しやすく、比較もしやすいということになります。
税抜経理のメリット③:固定資産の購入時に有利
「購入した備品の金額によっては一年で経費にできず、減価償却する必要がある」ということをご存じの方も多いのではないでしょうか。
基本的には10万円未満の備品は全額をその年の必要経費とすることができます。
しかし、10万円以上の備品を購入した際は、固定資産として貸借対照表に載せて、購入した備品の耐用年数に応じて減価償却することになります。
実は、この「10万円」という基準は、経理方法によって少し捉え方が異なります。
税込経理と税抜経理それぞれで、いくらまでの備品の購入なら全額その年の必要経費となるのか?表にまとめてみました。
| 経理方法 | 全額が必要経費となる基準 | その年に全額必要経費とできる金額(税込) |
|---|---|---|
| 税込経理 | 税込みで10万円未満 | 99,999円まで |
| 税抜経理 | 税抜きで10万円未満 | 109,999円まで |
上記の表のように、同じ「10万円未満」という線引きでも、経理方法の違いによって必要経費にできる備品の購入価格が違ってきます。
取得価額が〇〇円未満という基準は他にもあって、
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が使えるのは取得価額が100,000円~299,999円まで
- 一括償却資産として計上できるのは取得価額が100,000円~199,999円まで
という風にさまざまです。
どの処理方法を選ぶかは
- 少額減価償却資産の特例が使える要件を満たしているか
- その年の損益の見通し
- 繰越欠損金の有無
- 償却資産税が課税されるかどうか
などの観点から検討する必要があるので一概には言えませんが、税抜経理の方が税込経理よりも多い金額をその年の必要経費にできると言えます。
個人事業主向けの記事ですが、30万円未満の消耗品を買った時のベストな節税方法について解説した記事がありますので参考になさってください。
その年に全額経費にすることが節税になるのか?多くの経営者が気にされている情報が載っています。
税抜経理のメリット④:交際費の上限について
法人の場合、交際等の額は、原則としてその全額が費用にならないとされていますが、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人は交際費を費用にすることができます。
上記の法人は
- 年間800万円まで
- 飲食費のうち50%までの金額
いずれか大きい方を選択し、費用にすることができます。
交際費の範囲などの詳しい説明はこちらの国税庁のページをご確認ください。
この「800万円まで」「50%まで」という金額については、税抜経理を選択している場合は税抜金額で判定することになります。
そのため、例えば上記1を例にすると、年間の交際費が800万円を超えていたとしても、
税抜経理を選択していれば、税込金額で年間880万円までを費用にすることができます。
もともと交際費が多くない事業者は気にしなくていいのですが、
交際費の金額が多い業種にとっては税込か?税抜か?という違いは大きいのではないでしょうか。
税抜経理のメリット⑤:経審を受ける際に試算表を組み替える必要がない
税込経理のデメリットで解説したように、建設業の事業者が「経営事項審査」を受ける場合は「税抜表記の会計資料」を分析機関に提出する必要があります。
そのため、経審を受けることを考えている事業者は税抜経理を選択することで、経営状況分析申請の手間を削減することができます。
税抜経理のデメリット①:処理が煩雑になる
次は、税抜経理のデメリットについて解説していきます。
これまの説明の通り、税抜経理は
- 日々の仕訳登録の時に本体価格と消費税額を分けて登録する
- 固定資産台帳に登録するときは消費税を除いた本体価格のみを登録する
- 決算整理の時は仮受消費税と仮払消費税の相殺仕訳が必要
- 決算後に仮受消費税と仮払消費税が残っていないかチェックが必要
など、日々の記帳から決算整理の時まで常に消費税について気を配る必要があります。
そのため、小規模な事業者やひとり法人、経理担当の経験がまだ浅い場合などは処理が煩雑に思えるかもしれない点がデメリットです。
税抜経理のデメリット②:帳簿と自身の感覚の間にズレが生じる可能性がある
これはデメリットというより「違和感を抱く可能性がある」という点についてなのですが、
税抜経理の場合は消費税を除いた本体価格のみが会計に表示されます。
そのため、現金の出入りをベースに収入や支出流れを追っていると、
「自分の感覚と会計の載っている金額に乖離がある?」
と感じる可能性があります。
税抜経理の場合は、
- 収益や費用の本体価格は損益計算書に
- 一緒に受け取った(支払った)消費税は貸借対照表に
載っていることも、混乱を招く原因かもしれません。
ここまで税込経理と税抜経理についてさまざまな角度から解説してきましたが、中には
「手間はかけたくないから税込経理にしたいけど、消費税の予測はできた方がいいな…」
という方もおられると思います。
次の章では、そういった事業者向けに
税込経理でも消費税の納税額を予測できるのかどうかについて解説します。
税込経理でも消費税の納税額を確認する方法はあるのか
税込経理の場合は収益や費用に消費税が含まれた状態で会計入力を行うため、消費税の金額は損益計算書にも貸借対照表にも載っていません。
税込経理でも消費税の納税予測額を把握する方法はあるのでしょうか?

税込経理でも消費税の納税予測額を把握する方法はあります。
ただし、事業者によって選択している消費税の計算方法が異なるため、詳しい計算はこの記事では割愛させていただき、それぞれの計算方法に応じた概算額の出し方を別の記事で紹介したいと思います。(現在準備中です)
消費税の計算方法は、おおまかに分けて3つあります。
- 原則(一般課税)
- 簡易課税
- 2割特例を使った計算方法
「消費税の仕組みそのものでさえ難しいのに、3種類もあったら覚えられない!」という方もいらっしゃると思います。
基本的には、
| 消費税の計算方法 | 適用条件 |
|---|---|
| 原則(一般課税) | 基準期間もしくは特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者のうち、簡易課税を選択しない場合、自動的に適用される |
| 簡易課税 | 期限内に消費税簡易課税制度選択届出書を出さない限り適用されない (一度選択すると2年間継続必須) |
| 2割特例 | インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった場合に他の計算方法と比較し有利選択できる |
というものです。
どの計算方法であっても税込経理の事業者が期中に消費税の予測額を把握することは可能となっていますので、他の記事の完成を楽しみにお待ちいただけますと幸いです。
まとめ
長くなりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございます。
最後にこの記事で解説したことをまとめたいと思います。
まとめ
- 税込経理とは、取引金額に消費税を含めた金額で会計処理を行う方法のこと
- 税抜経理とは、取引金額と消費税を分けて仕訳をする会計方式のこと
- 税込経理と税抜経理は自由に選択できるが、原則としてすべての取引に共通して同じ経理方法をする必要がある
- 免税事業者は税込経理で会計処理を行う
- 税込経理と税抜経理では消費税の決算整理仕訳の方法が異なる
- 税込経理は記帳や固定資産の管理が簡潔だが、期末まで納税額が分からないというデメリットがある
- 税抜経理は消費税の納税額が把握しやすく、消費税率改定の影響を受けにくく、10万円以上の備品・固定資産の購入に有利で交際費の上限が上がるなどメリットが多いが、処理が煩雑である
- 税込経理でも期末までに消費税の予測額を把握することは可能
※別の記事を執筆中です
税抜経理の方がメリットが多いですが、日々の記帳にかかる時間や疑問が生じた際にかかる手間ひまを考えて税込経理を選択する事業者もいらっしゃいます。
- どちらの方が自分の会社に合っているか?
- 税込経理にしたいけど、消費税の納税額も把握しておきたい
など、経理方式の選択に関するお悩みがある方は弊社にご相談ください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
弊社では、決算や確定申告までに消費税の予測納付額をお伝えしています。
お客様のご要望に応じて税込経理でも税抜経理でも記帳が可能で、
「消費税を納めるまでいくら払うことになるのか分からず不安」
という方のために会計に消費税の納付額を反映させることも可能です。
また、初回のご面談は無料で記帳代行や毎月の顧問契約についてのご相談をしていただくこともできます。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
まずはお気軽に問い合わせください。
\24時間365日受付中 /
『会計税務顧問サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。