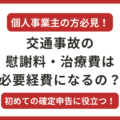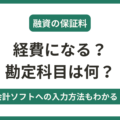こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
お客様から、「前回の決算で消費税を納付したのにすぐに消費税の中間納付を払わないといけない!」という声を聴きます。
中小企業の経営者や個人事業主の方にとって、消費税の中間納付は資金繰りに大きな影響を与える事があります。消費税の中間納付は分割をすることはできますが、減額申請を行って減額をすることはできません。
ただ、前期にたまたま利益が多く出たため、消費税の中間納付税額が一時的に増加した時など特定のケースでは「仮決算方式」で申告する事で消費税の中間納付税額を抑える事ができます。
今回は「仮決算方式」について数値例を使って説明いたします。
目次
制度の基本:中間納付・中間申告とは
対象者と要件
- 消費税の前課税期間(前年度など)における確定の消費税(国税分)の納税額が 48 万円を超える事業者は、翌課税期間中に中間申告・中間納付が必要になります。
- 前年度納税額が 48 万円以下の場合、義務はありませんが、「任意の中間申告制度」の届出をすれば中間申告を行うことも可能です。
中間申告の回数・期限
前年度消費税額(国税分)金額によって、年間に中間納付をする回数が決まっています。
- 48 万円超~400 万円以下 → 年 1 回
- 400 万円超~4,800 万円以下 → 年 3 回
- 4,800 万円超 → 年 11 回
各回の中間申告の法定納期限は、その対象期間末日の翌日から 2 か月以内と定められています。例えば、3月決算の会社で年1回の中間納付が必要な場合、中間申告の対象期間は4月~9月。法定納期限はその対象期間末日の9月30日から2か月後の11月30日が納期限になります。
予定方式(前年実績方式)と仮決算方式の違い
消費税の中間申告は2パターンを選択することができます。予定方式(前年実績方式)と仮決算方式です。基本は予定方式(前年実績方式)で決められた中間納付税額を法定期限までに納める事になります。
| 項目 | 予定方式 | 仮決算方式 |
|---|---|---|
| 税額の基準 | 前年度の消費税額(国税分)を基に、定められた割合で分割 | 中間期間(例:期首から6か月など)を擬似的に「課税期間」と見なし、その実績売上・仕入に基づいて消費税を計算 |
| 税額の柔軟性 | 業績変動を反映できない | 実績を反映できるため、業績悪化時には税額を抑えられる可能性あり |
| 申告・計算の手間 | 比較的簡便 | 仮決算を行う必要があるため、会計的な手間が増える |
| マイナス税額・還付 | 通常の予定方式では「納付すべき」方式なので中間で還付はない | 仮決算で計算上マイナス(控除超過)になっても中間申告段階では還付できず、中間申告税額は “0 円” 扱いとなる(還付は本決算時に精算) |
| 精算処理 | 中間で納付した額を確定申告時に控除 | 同様に確定申告で精算・控除 |
予定方式(前年実績方式)は前年度の消費税額(国税)を基に中間納付税額が決まるため、前期の利益が上がったことにより前年度の消費税が多額になった時は、中間納付税額も多額になってしまいます。
仮決算方式は今年度の実績を基に消費税額を計算します。ただ、計算して税額が0円未満になったとしても還付にはなりません。
仮決算方式が納付税額を抑えられるケースとは?
仮決算方式を選択して、「前期に比べて今期の実際の中間業績が悪化している」ケースまたは「仕入・設備投資が増えている」ケースだと、予定方式(前年実績方式)で納めるよりも中間納付額を抑えられることがあります。以下のような状況がその典型例です。
有利になる典型ケース
- 売上が前期に比べて大幅に落ちている
→ 消費税の課税売上が減ることで売上に関する消費税額が小さくなり、納付すべき税額が少なくなる可能性があります。前期にたまたまスポットの売上がでて、今期は通常の売上に戻っている場合もこのケースに該当します。 - 仕入や経費など控除対象が大きくなっている
→ 仕入や経費が増えることで、消費税の控除税額が大きくなります。売上に関する消費税額に対して消費税の控除税額が追いつくと、差し引きで税額が減ります。 - 非課税売上の割合が上がった
→ 課税売上の比率が下がると、課税ベース自体が小さくなります。 - 設備投資など先行投資をして仕入増となっている
→ 初期段階で仕入が先行する事業などでは、上期に消費税の控除が膨らみ、税額を相当に抑えられることがあります。
ただし、仮決算方式を使って多額の消費税額を納付しておき、確定申告で消費税の還付受けているケースがあります。この場合、消費税の還付と利息に当たる還付加算金が支払われていましたが、現在は中止されています。
数字例で比較する:仮決算方式で有利になるパターン
以下の数字例で、予定方式と仮決算方式を比較してみます。
前提条件
- 事業年度:4月~翌年3月
- 前課税期間(前年度)における確定消費税: 600 万円
- 中間申告回数:年 3 回(400 万~4,800 万円の範囲)
- 各回(4~6月、7~9月、10~12月)の予定方式基準:前年度税額 600 万円 ÷ 4 = 150 万円ずつ(3回分)
- 今期上期(4~9月)の仮決算実績を以下のように仮定
| ケース | 課税売上(税抜) | 課税仕入・控除対象仕入(税抜) |
|---|---|---|
| 標準ケース | 5,000 万円 | 4,000 万円 |
| 売上が落ちこんだケース | 3,000 万円 | 2,800 万円 |
| 仕入・投資先行ケース | 4,500 万円 | 4,800 万円 |
消費税率を 10%と仮定。
各ケースでの仮決算方式による中間納付額
- 標準ケース
売上消費税:5,000 万円 × 10% = 500 万円
仕入控除税額:4,000 万円 × 10% = 400 万円
→ 差引税額:100 万円 - 売上が落ちこんだケース
売上消費税:3,000 万円 × 10% = 300 万円
仕入控除税額:2,800 万円 × 10% = 280 万円
→ 差引税額:20 万円 - 仕入・投資先行ケース
売上消費税:4,500 万円 × 10% = 450 万円
仕入控除税額:4,800 万円 × 10% = 480 万円
→ 差引税額:‐30 万円 → 中間申告上は 0 円 扱い(マイナスでも還付はなし)
予定方式 vs 仮決算方式での比較
| ケース | 予定方式(中間納付額) | 仮決算方式(中間納付額) | 差額/コメント |
|---|---|---|---|
| 標準ケース | 150 万円 | 100 万円 | 仮決算方式の方が 50 万円節税可能 |
| 売上が落ち込んだ型 | 150 万円 | 20 万円 | 130 万円も節税できる可能性 |
| 仕入・投資先行型 | 150 万円 | 0 円 | 実質的に納付を先送り可能(中間段階では支払なし) |
このように、売上が低下している場合や仕入や控除対象が先行している場合には、仮決算方式を選ぶことで中間段階での納付税額を大きく抑えることが可能となります。
仮決算方式を使う際の注意点
- 中間申告期限の遵守が必須
仮決算方式を選ぶ場合、その中間申告期限までに申告・納付をする必要があります。申告期限までに申告・納付をしない場合は予定方式(前年実績方式)で消費税の中間納付をします。 - マイナス税額=還付不可
仮決算で消費税の差し引き税額がマイナスになっても、中間段階での還付は認められていません(税額は 0 円 扱い)。本決算で精算されます。 - 会計・帳簿整備が重要
期中で売上・仕入・控除対象・非課税売上などを正確に把握できるよう会計帳簿への入力がされている必要があります。 - 消費税の申告が複数回必要になる。
仮決算方式は仮とはいえ決算なので、確定申告と同様に消費税の申告書を作成してその申告書の申告をします。また、確定申告は確定申告で消費税の申告書を作成して申告をします。申告書の作成とその申告回数が増えるため、税理士報酬も高くなります。
まとめ:仮決算方式を選ぶべきタイミング
- 今期の売上が前年に比べて大きく減少している
- 仕入・控除対象支出が先行して発生している
- 非課税売上の割合が上昇して課税ベースが縮小傾向にある
- 帳簿管理体制が整っており、仮決算を期中で行える余力がある
これらの条件が重なっているときは、予定方式より仮決算方式を選ぶことで中間納付額を抑え、資金繰りの改善につなげられる可能性があります。
ただし、仮決算方式を使うかどうかは事業者が選べる制度ですので、自社のキャッシュフロー、会計能力、事業の予測などを勘案しながら判断するのがよいでしょう。必要なら税理士に相談するのが安全です。
自社の経理をご自身で行っておられる経営者の方へ
弊社は
- 記帳代行のみのご依頼
- 月次顧問のご依頼
- 年1回の決算/確定申告のご依頼
などのサービスを行っている顧問先数700社超、クラウド会計導入実績300社超の税理士法人です。
- より効率的な自計化を進めたい
- 利益が出ているはずなのにキャッシュが減っており原因が分からない
- クラウド会計を導入して事務負担を軽減したい
など、お客様に寄り添ったサービスの提供が可能です。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
初回のご相談は無料ですので、会計や税務・経営に関するお悩みがある方はお気軽にご相談ください。
\24時間365日受付中 /
『確定申告サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。