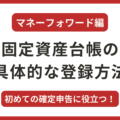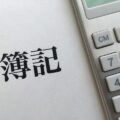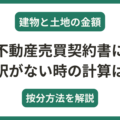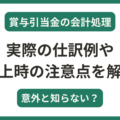こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
今回は納品書に消費税の記載が必要かどうかについてご説明します。
経理業務をしていると、①納品書に消費税の記載が必要だったかな?②そもそもなぜ必要なのかな?このような疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では納品書と消費税の関係、それにインボイス制度を絡めながら説明をしていきます。
最後に、納品書に消費税を記載しないことのデメリットについても触れますので最後まで読んでいただけると幸いです。
是非、参考にされてください。
納品書に消費税の記載は必要ですか?
いきなり本題に入りますが、答えは「はい」です。
納品書に消費税の記載は「必須」ではありませんが、記載することが強く推奨されます。実務的にも、多くの企業が消費税額を明記しています。
納品書に消費税の記載が「必須でない」理由
納品書は法律で定められた書類ではなく、取引の証拠として任意で発行されるものです。そのため、法的には消費税の記載義務はありません。
記載が推奨される理由
取引の明確化
税抜価格と消費税額、税込合計が明記されていると、自社と取引先での認識のずれを防げます。
会計処理や請求書との整合性
請求書ではインボイス制度(適格請求書)により、消費税額の記載が必要です。
納品書にも同様の情報があると、会計処理がスムーズになります。
インボイス制度との整合性(2023年10月~)
インボイス(適格請求書)制度開始以降は、納品書でもインボイス情報を記載する企業が増えています。
ただし、納品書自体はインボイスの対象書類ではありません。
最後に、具体的な記載例は下記のとおりです。

ポイント!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 消費税の記載義務 | なし(任意) |
| 記載を推奨する理由 | 誤解防止、会計処理、インボイス対応など |
| インボイス制度との関係 | 納品書は対象外だが、記載が実務上望ましい |
納品書と消費税の関係を教えてください!
次は、納品書と消費税の関係についてご説明します。
①納品書とは何か?②それと消費税がどう関係するのか?③そして最近始まったインボイス制度との関係について出来るだけ分かりやすくご説明します。
納品書とは
納品書は、商品やサービスを納品したことを証明するための書類です。主に以下のような情報を記載します。
- 納品日
- 納品先
- 商品名・数量・単価・金額
- 小計・場合によっては消費税・合計金額
※法律で発行が義務付けられている書類ではなく、取引上の慣習で使われています。
消費税との関係
ここからは納品書と消費税の関係をご説明します。
【1】納品書自体には消費税の記載義務はない
納品書は請求書や領収書のような法定書類ではないため、消費税額を明示する法的な義務はありません。記載が「必須でない」理由でご説明したとおりです。
しかし、多くの事業者は「明細としてわかりやすい」ため、消費税額を明記して発行しています。
【2】インボイス制度(適格請求書等保存方式)との関係
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、消費税の仕入税額控除のために、以下の情報が必要になります。
適格請求書の要件(一部)
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとの消費税額
- 税率ごとの金額
- 発行者の氏名・名称
ただし、「納品書」はインボイス(適格請求書)の対象書類ではありません。
→ つまり、納品書にインボイス要件を満たす義務はありません。
【3】実務的には「請求書の補助資料」として機能
請求書と合わせて納品書も保管する会社が多いため、納品書にも消費税が記載されていると整合性が取りやすいです。
また、社内の仕入・経費処理で納品書を使う会社もあるため、消費税額が書いてある方が実務上便利です。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品書の法的位置付け | 任意の書類(発行義務なし) |
| 消費税の記載義務 | なし(ただし記載推奨) |
| インボイス制度との関係 | 消費税や税込合計の記載があると、会計処理がスムーズ |
| 実務上の対応 | 消費税や税込合計の記載があると、会計処理がスムーズ |
納品書に消費税を記載しないデメリットはありますか?

納品書に消費税を記載しないとデメリットがあります!
はい、納品書に消費税を記載しないことにはいくつかのデメリットがあります。法的な違反にはなりませんが、実務上や取引先との関係で問題が生じる可能性があります。
以下に、主なデメリットを整理してご紹介します。
納品書に消費税を記載しない主なデメリット
① 取引先との誤解が生まれる可能性
消費税の記載がないと、「金額は税込か?税抜か?」が不明確になります。
取引先から「請求金額が納品書と違う」と問い合わせが来ることもあるでしょう。
特に、消費税が大きな金額になる場合はトラブルの原因になりやすいです。
対応策:税抜・税込のいずれかを明確に記載する(例:「※金額はすべて税込です」など)
② 請求書との整合性がとりにくくなる
多くの企業では納品書 → 請求書 → 支払処理という流れになっています。
納品書に消費税がないと、請求書との金額の差異が発生して混乱しやすいです。
例:納品書では10,000円、請求書では11,000円(消費税含む)
→ 「どっちが正しいのか?」と社内・取引先で確認の手間が発生してしまう
③ 社内の会計・経理処理が煩雑になる
経費精算や原価計算の際に、納品書をベースに処理するケースもあります。
消費税が記載されていないと、経理担当者がいちいち税率計算をしなければならず非効率です。
特に、軽減税率(8%)と標準税率(10%)が混在する取引では要注意です。
④ 税務調査時に説明が難しくなる可能性
納品書は正式な会計証憑ではありませんが、補足資料として提出を求められることがあります。
消費税額が書かれていないと、取引内容や課税区分の確認に手間がかかる可能性があります。
まとめ
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| 誤解の発生 | 税抜・税込の不明確さでトラブルの原因になりやすい |
| 書類不整合 | 請求書と納品書の金額が一致せず現場が混乱 |
| 経理の非効率 | 社内経理処理でも再計算の手間が増える |
| 税務調査対応の負担 | 記載がないと説明が難しくなることがある |
最後に

いかがでしょうか。
結論:原則として「消費税は記載する」方が無難です。
法的には不要ですが、実務上は記載した方がトラブルや手間を防ぐことができます。
少なくとも、「税抜」「税込」のどちらかであることは明記するのが最低限の対応だと思います。
是非参考にされてみてください。
自社の経理をご自身で行っておられる経営者の方へ
弊社は
- 記帳代行のみのご依頼
- 月次顧問のご依頼
- 年1回の決算/確定申告のご依頼
などのサービスを行っている顧問先数700社超、クラウド会計導入実績300社超の税理士法人です。
- より効率的な自計化を進めたい
- 利益が出ているはずなのにキャッシュが減っており原因が分からない
- クラウド会計を導入して事務負担を軽減したい
など、お客様に寄り添ったサービスの提供が可能です。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
初回のご相談は無料ですので、会計や税務・経営に関するお悩みがある方はお気軽にご相談ください。
\24時間365日受付中 /
『確定申告サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。