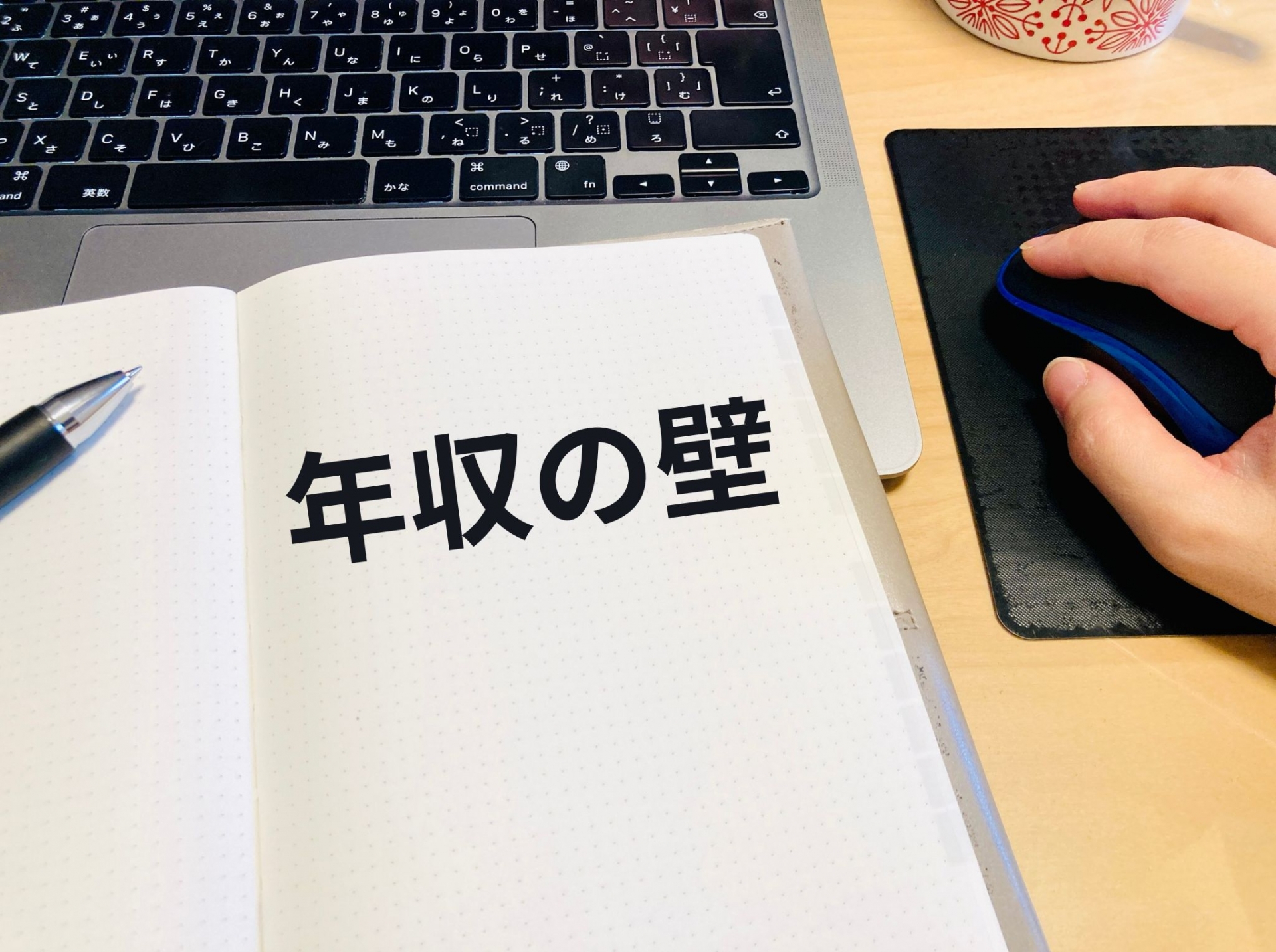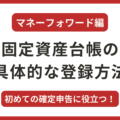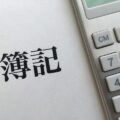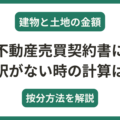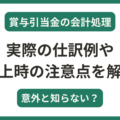こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
年末調整のシーズンが近づいてきました。
自社で年末調整処理を行う経理担当者の方にとって、2025年(令和7年)からの変更点は押さえておきたいポイントです。
この記事では、最新の控除改正や実務対応のポイントをわかりやすくまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
給与所得控除の下限額引き上げ
給与所得控除の下限額が55万円→65万円に引き上げられました。
対象:給与収入190万円以下の社員
給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除には変更はありません。
基礎控除額の改正と所得段階制の導入
2025年分は基礎控除額が一律48万円から、所得に応じて58万円〜95万円に段階的に引き上げられます。
所得金額に応じた基礎控除の金額は下記のようになります。
| 給与収入金額(万円) | 合計所得金額(万円) | 基礎控除額(万円) |
|---|---|---|
| ~204 | ~132 | 95 |
| 204~475 | 132~336 | 88 |
| 475~655 | 336~489 | 68 |
| 655~850 | 489~655 | 63 |
| 850~2,545 | 655~2,350 | 58 |
| 2350~2,400 | 48 | |
| 2,400~2,450 | 32 | |
| 2,450~2,500 | 16 | |
| 2,500~ | なし |
※「合計所得金額」は社会保険料控除、基礎控除などの所得控除を差し引く前の所得金額の合計です。
年末調整が可能な給与収入2,000万円未満の場合、所得金額に応じて95~58万円の間で基礎控除額が変わることになりますので、注意しましょう。
特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満で一定の所得範囲の親族を扶養している場合、3万円〜63万円の控除が受けられる「特定親族特別控除」が新設されました。
所得金額に応じた特定親族特別控除の金額は下記のようになります。
| 給与収入金額(万円) | 合計所得金額(万円) | 控除額(万円) |
|---|---|---|
| 123~150 | 58~85 | 63 |
| 150~155 | 85~90 | 61 |
| 155~160 | 90~95 | 51 |
| 160~165 | 95~100 | 41 |
| 165~170 | 100~105 | 31 |
| 170~175 | 105~110 | 21 |
| 175~180 | 110~115 | 11 |
| 180~185 | 115~120 | 6 |
| 185~188 | 120~123 | 3 |
※「合計所得金額」は社会保険料控除、基礎控除などの所得控除を差し引く前の所得金額の合計です。
なお、特定親族特別控除は誰か1人にのみ適用が可能です。例えば、下記のような場合です。
①2人以上の居住者の特定親族に該当
例えば父・母が共働きの場合、どちらか一方でしか特定親族特別控除を適用できません
②子が結婚して夫となる人の配偶者特別控除の対象となる場合、夫の配偶者特別控除か、父もしくは母の特定親族特別控除かどちらか一方しか適用できません。
③兄弟姉妹間で双方が特定親族に該当する場合、どちらか一方でしか適用できません。
年末調整を行う方の家族情報、そのご家族の所得金額の把握に漏れがないように注意しましょう。
扶養親族・配偶者等の所得要件の引き上げ
扶養控除や配偶者控除の所得基準が「48万円以下」から「58万円以下」に緩和されました。
合計所得金額が58万円以下の場合に、扶養控除・配偶者控除を受けられることになります。
配偶者特別控除については、下限額が48万円から58万円に変更になりますが、所得金額に応じた段階制の控除金額に変更はありません。
勤労学生控除の所得要件引き上げ
勤労学生控除は、給与所得や事業所得がある学生本人が対象となります。
控除額27万円は変更なしで、令和7年分から所得要件が以下のように変更されます。
令和6年分まで:合計所得金額75万円以下
令和7年分(2025年分):合計所得金額85万円以下
勤労学生控除は、学生本人の所得制限がある控除です。扶養控除とは別に計算されるため、親の年末調整で扶養控除の適用を判断する際には、学生本人の所得状況も確認しておく必要があります。
ひとり親控除の所得要件引き上げ
ひとり親控除は、離婚や死別などで子どもをひとりで養育している親が対象となります。
控除額は35万円は変更なしで、扶養する子の所得要件が令和7年分から変更されます。
令和6年分まで:扶養する子の合計所得金額48万円以下
令和7年分(2025年分):扶養する子の合計所得金額58万円以下
控除額自体に変更はありませんが、所得要件が10万円引き上げられたことで、控除の適用対象となる子どもが増える可能性があります。
年末調整では、扶養する子の所得状況を正確に把握し、漏れなく申告を受けることが重要です。
申告書の様式変更
前述の改正によって、各申告書の様式が変更になります。
令和7年分の各申告書は下記の通りです。
| 申告書 | ポイント | 国税庁様式 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 申告書 記載例 | |
| 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 | 基礎控除・扶養控除・配偶者(特別)控除・給与所得控除改正に伴う数値修正。特定親族特別控除追加。 | 申告書 記載例 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 申告書 記載例 |
まとめ
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和7年分) | ポイント・補足 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除 下限額 | 55万円 | 65万円 | 対象:給与収入190万円以下。超過分は変更なし。 |
| 基礎控除額 | 一律48万円 | 所得段階制で58〜95万円 | 所得に応じて変動。年収2,000万円未満は58〜95万円の間。 |
| 特定親族特別控除 | なし | 新設 3万円〜63万円 | 19歳以上23歳未満で一定の所得の親族が対象。1人のみ適用可能。申告書への記載必須。 |
| 扶養控除・配偶者控除 所得要件 | 48万円以下 | 58万円以下 | 所得要件が10万円引き上げ。配偶者特別控除は段階制の控除金額に変更なし。 |
| 勤労学生控除 | 合計所得75万円以下 | 合計所得85万円以下 | 控除額27万円は変更なし。本人の所得制限。扶養控除とは別。 |
| ひとり親控除 | 扶養子の所得48万円以下 | 扶養子の所得58万円以下 | 控除額35万円は変更なし。所得要件のみ10万円引き上げ。 |
| 申告書様式 | 前年版 | 改正に対応した令和7年版 | 基礎控除・給与所得控除の改正、特定親族特別控除追加、扶養控除等の数値修正。 |
令和7年(2025年)分の年末調整では、給与所得控除や基礎控除、扶養控除・配偶者控除など、多くの控除額や所得要件が改正されます。特に「特定親族特別控除」の新設や、各控除の所得要件引き上げは、従業員の手取りや年末調整の計算に直接影響するため、経理・総務担当の方は注意が必要です。
年末調整をスムーズに進めるためには、改正点を押さえた上で、最新の申告書を従業員に配布し、漏れなく回収することが大切です。また、所得金額や扶養状況を正確に把握し、計算ミスを防ぐことも重要です。
本記事でご紹介した改正内容と実務ポイントを参考に、2025年の年末調整を安心して進めましょう。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。