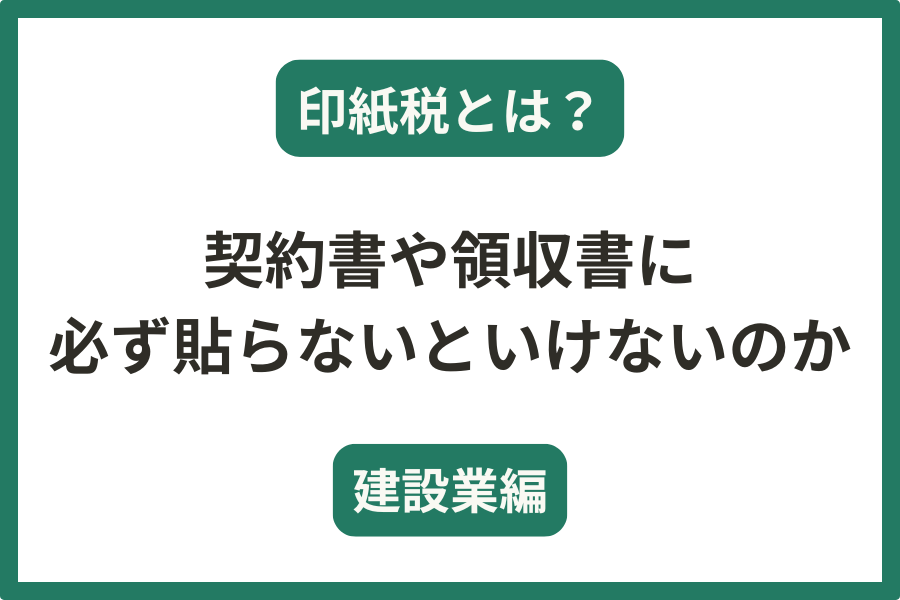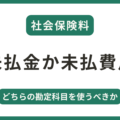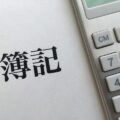こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
今回は不動産業編に引き続き印紙税についてご説明します。
印紙税は、国内において特定の文書を作成する際に課税される税金です。
この税は、主にビジネス上の取引に関連する文書に適用されます。
これを課税文書と言います。
つまり、課税文書を作成することにより課税されます。
印紙税は以外と細かな規定があります。
今回は建設業の印紙税に絞ってお伝えします。
是非、参考にされてください。
建設業で印紙税が関係する文書の例
①工事請負契約書
工事請負契約書は、建築・土木工事の請負に関する契約を交わす際に、注文者と請負者との間で締結される契約書です。工事請負契約書の印紙税は次のことを覚えておいてください。
- 請負とは、請負者がある仕事の完成を約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいいます。
- 請負は、完成された仕事の結果を目的とする点が特徴です。
- 実際の取引においては混合契約となるものが多く、印紙税法上どの契約としてとらえるべきものであるか判定の困難なものが多く見受けられるので注意が必要です。
- 請負契約の契約書は課税文書で第2号文書となります。
②変更契約書(増額・減額)
請負金額に変更があった場合の契約書も印紙税の対象となります。
変更契約書が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかによります。原契約書により証されるべき事項のうち「重要な事項」を変更するために作成した変更契約書は課税文書に該当し、「重要な事項」を含まない場合は課税文書に該当しません。
変更契約書がどの号の文書に該当するかは、次のとおりです。
⑴ 原契約書が課税物件表の1つの号の文書のみに該当し「重要な事項」を変更するとき
原契約書と同一の号の文書としての取り扱いです。
⑵ 原契約書が課税物件表の2以上の号に該当するとき
- 2以上の号のいずれか一方のみの「重要な事項」を変更するものは、その一方の号の文書として取り扱われます。
- 2以上の号のうち2以上の号の「重要な事項」を変更するものは、それぞれの号の文書に該当した上で、印紙税法別表第1「課税物件表の適用に関する通則」3の規定に基づいて最終的な所属が決定されます。
③覚書・確認書
請負契約の一部変更などを記載する場合も、内容により印紙税が課税される場合があります。
覚書・確認書のような契約当事者の一方が署名押印して相手に交付するような文書でも、その文書によって契約が成立となるものは、通常の契約書による文書ではなくても印紙税法上は契約書に該当します。
④注文書・請書
注文請書とは、受注者が発注者の注文を確実に引き受けたことを意思表示するために発行する書類です。発注者からの注文内容を確認して問題が無ければ受諾の意思を正式に伝え、後のトラブルを防ぐために行います。法的な発行義務がある書類ではありませんが、取引内容を明示するために発行されます。特に企業間同士の取引では用いられることが多いです。
⑴ 請負契約の注文請書の場合
請負契約の注文請書は収入印紙が必要です。請負契約の注文請書は契約に合意し成立したことを証明するものだからです。印紙税の課税物件表上、第2号文書になり1万円以上の注文請書には収入印紙が必要となります。
⑵ 売買契約の注文請書の場合
売買契約の注文請書は、物品の譲渡契約に該当することから、第2号文書せず収入印紙は必要ありません。
④領収書
建設業に限りませんが、5万円以上の領収書には、200円の収入印紙が必要です。
印紙税が不要なケース

印紙税が不要な文書もあります。
以下の文書には印紙税がかかりません。
- 契約金額が記載されていない請負契約書:金額がなければ「課税文書」に該当しないためです。
- 電子契約で作成・保存される文書:紙で出さなければ「課税文書」に該当しないためです。
- 見積書・納品書・請求書:契約の成立を示さなければ不要です。
- 注文書・請書(契約成立を示さないもの):契約書代わりになると課税されます。
- 契約の「写し」や「控え」:原本には印紙が必要ですが、控えは不要です。
- 契約が外国で作成された文書:日本国内で使用されない契約書などは印紙税の対象外です。
印紙税を軽減する方法
① 電子契約
印紙税は紙の文書に課税されます。そのため、電子で交わした契約書には課税されません。例えば、クラウド型の電子契約サービス(クラウドサイン・GMOサイン・DocuSignなど)を用いることで節税できます。また、電子データの真正性が求められるため、タイムスタンプや電子署名のある正式な電子契約が必要となります。単なるPDFのメール送付では正式な電子契約とは言えません。
② 文書の性質の見直し(契約書ではない形式への変更)
印紙税は課税文書に課されます。見積書・注文書・注文請書の組み合わせによっても、契約の意思が明確であるなら契約が成立しているとみなされます。そのため、あくまで見積内容の確認に止めた文書にすれば直ちに課税文書とされる可能性は低いと言えます。あくまで実質的な判断になりますので気を付けましょう。双方の合意が明示されておらず契約成立の証拠とならない場合に課税文書にならないと判断されることになります。
③ 印紙税の非課税範囲の活用
実務ではあまり多くないケースにはなりますが、請負金額が1万円未満の場合は印紙税は不要です。また、請負契約書で工事が無償(0円)の場合は印紙税は非課税となります。このようにそもそも印紙税が非課税になる要件を満たすのであれば、印紙税は不要となります。
④ 課税文書の整理と社内ルール整備
社内でルールを決めて印紙税の無駄な支払いを避けるように運用することも有効です。
- 書類のひな形を統一して契約成立の文言を避ける
- 1万円以上の契約は電子契約を原則にする
- 書面で契約が必要な場合にのみ印紙を貼るような承認フローにする
- 月次で印紙税の支払い履歴をチェックする
⑤ 誤って印紙を貼った場合の印紙税過誤納確認申請をする
印紙を貼らなくてもよかった文書に貼ってしまった場合、印紙税過誤確認申請をすることで印紙税が返金される可能性があります。還付請求先は、所轄の税務署です。必要書類は、原本・印紙・印紙税還付確認申請書などです。申請期限は、印紙を貼った日から5年以内です。期限がありますので期限切れにならないように注意しましょう。
印紙税を貼らないとどうなるか
印紙税の注意点をお伝えします。
①具体的なリスク
⑴ 少額取引を装った場合
金額分割による少額取引を装うと脱税とみなされるリスクがあります。
⑵ 電子契約後の書面の交付
電子契約後に紙を原本として交付すると、その紙は課税対象になる可能性が高いです。
②具体的なペナルティ
⑴ 過怠税によるペナルティ
印紙の貼り忘れや金額不足の場合、納付すべき印紙税額の3倍が過怠税として課税されます。
消印を忘れると、その額面相当額(本税と合わせると2倍)が課税されます。
税務署へ未納額を自主申告した場合は、過怠税が印紙税額の1.1倍に軽減されます。
⑵ 刑事罰の可能性
不正な手段で印紙税を免れた場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科の可能性あり)が科される可能税があります。
また、単に印紙を貼らなかった場合でも1年以下の禁固または50万円以下の罰金が、消印忘れの場合でも30万円以下の罰金が科される可能性があります。
⑶ 追徴額・財務負担
例として、某コンビニエンスストアで60万通の課税文書で200円の貼り付け漏れが発覚しました。その納付漏れによる税額は約1.2億円にものぼり、過怠税が約1.5億円の追徴をされたケースもあります。
⑷ 税務調査
過去5年間の課税文書が対象となり、遡及して追徴課税される可能性があります。
大量生産や定型取引の文書には、特に重点的に調査が及ぶ可能性があります。
⑸ 信用リスク
印紙税法違反が発覚し報道されると、企業のイメージや取引先・お客様からの信頼の低下に繋がる可能性があります。
特に脱税として世間に受け止められると、風評被害も発生しやすく、回復に時間とコストがかかります。
建設業でよくある質問
① 工事請負契約書には印紙が必要ですか?
必要です。建設工事の請負契約書は、印紙税法別表第一の第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。契約金額に応じて所定の印紙を貼付する必要があります。
② 契約金額が記載されていない請負契約書は課税対象ですか?
課税対象になります。契約金額が記載されていない場合でも、契約内容が明確であり、金銭の支払いが予定されている請負契約書であれば印紙税の課税対象です。ただし、記載金額がない場合は、最低額の印紙(200円)を貼付するのが一般的です。
③ 見積書には印紙が必要ですか?
通常は不要です。見積書単体では印紙税の課税対象外ですが、契約の成立を証明するものとして使用される場合(例えば、注文書と見積書をあわせて契約書とみなされるケース)には、課税対象とみなされる可能性があります。
④ 注文書・注文請書は印紙税の対象ですか?
場合によります。
- 注文書や注文請書が、契約書としての性質を持つ場合には(つまり、工事内容や金額、納期などの明確な記載があって両者が合意している場合など)、請負契約書とみなされて印紙が必要です。
- 単なる発注の意思表示であれば不要です。
⑤ 工事の追加契約(変更契約)には印紙が必要ですか?
必要です。追加工事や変更契約を別途書面で締結する場合、それは新たな請負契約書とみなされて印紙税の課税対象となります。追加金額に応じて印紙税が課税されます。
⑥ 契約書を2通作成する場合、それぞれに印紙が必要ですか?
はい。契約書を2通作成し、甲乙それぞれが1通保管する場合、それぞれの文書が課税対象となるため、2通分の印紙が必要です。
最後に
建設業の取引では1件ごとの金額が大きいため、印紙税の額も高額になりがちです。
また、税務調査で未納が発覚すると3倍の過怠税が課されることもあるため、非常に重要です。
ご不明な点や具体的な手続きについては、最寄りの税理士などの専門家にご相談ください。
印紙税を知ることは、コスト管理などの節税につながるのは当然のこととして、電子契約書に移行するなど事務作業の効率化にもつながります。是非実行してみてください。
自社の経理をご自身で行っておられる経営者の方へ
弊社は
- 記帳代行のみのご依頼
- 月次顧問のご依頼
- 年1回の決算/確定申告のご依頼
などのサービスを行っている顧問先数700社超、クラウド会計導入実績300社超の税理士法人です。
- より効率的な自計化を進めたい
- 利益が出ているはずなのにキャッシュが減っており原因が分からない
- クラウド会計を導入して事務負担を軽減したい
など、お客様に寄り添ったサービスの提供が可能です。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
初回のご相談は無料ですので、会計や税務・経営に関するお悩みがある方はお気軽にご相談ください。
\24時間365日受付中 /
『確定申告サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。