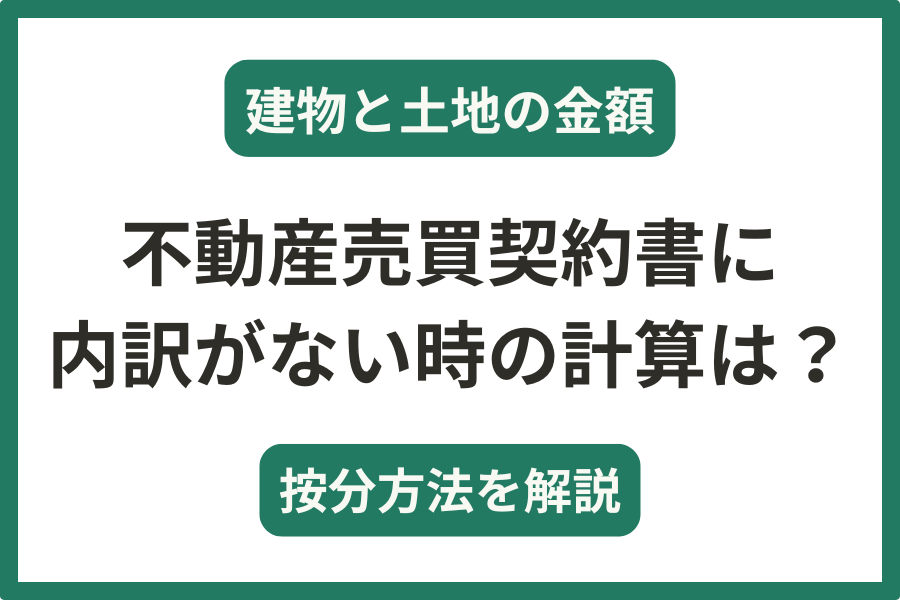こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
不動産の売買契約書を見たら、土地と建物の金額がバラされていない…
実はこのケース、意外と多くあります。しかし、税務処理や会計処理では必ず土地と建物の金額を分ける必要があります。「土地と建物の金額がいくらになるか?」は不動産の再販をされる事業者にとっては消費税の金額や利益に直結しますし、不動産オーナーにとっては、建物の金額は毎年の減価償却費に大きな影響を与えます。
この記事では、税理士の視点から「なぜ内訳が必要なのか」「内訳がない場合の按分方法」「実務上の注意点」を、具体的な数字例を交えて詳しくご紹介します。
なぜ内訳が必要なのか
売買契約書に記載がなくても、税務計算のためには土地と建物を分ける必要があります。理由は以下の通りです。
- 建物は減価償却の対象だが、土地は償却できない
- 固定資産税評価額や取得費の計算のため、税務署は内訳を求める
- 将来の譲渡所得計算(売却時)でも、取得価額を土地と建物に分けて把握しておく必要がある
- 不動産の再販業者にとっては建物の金額がいくらになるかで消費税の納付金額が変わる
内訳がない場合は、オーナーにとっては正確な確定申告ができず、不動産の再販業者の方も正確な会計処理や納付する消費税を含めた利益計算ができなくなります。
内訳がない場合の按分方法
ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。
① 固定資産税評価額の比率を用いる方法
最も一般的で実務上多用される方法です。評価額が土地と建物が別々に記載されており、税務的に否認されにくい方法です。
例
- 固定資産税評価額(建物):1,200万円
- 固定資産税評価額(土地):1,800万円
- 合計:3,000万円
売買契約書に「総額3,000万円」としか書かれていない場合、以下のように按分します。
- 建物:3,000万円 × (1,200 ÷ 3,000) = 1,200万円
- 土地:3,000万円 × (1,800 ÷ 3,000) = 1,800万円
固定資産税評価額の比率を使うことで、合理的かつ客観的な按分が可能です。
② 標準的な建築単価を利用する方法
建物の築年数や構造に応じて、標準的な建築単価(1㎡あたりの単価)を参考に建物の評価額を算定し、残余を土地とみなす方法です。
例
- 延床面積:100㎡
- 標準的な建築単価(木造、築20年):1㎡あたり12万円
- 建物価額:100㎡ × 12万円 = 1,200万円
売買契約書の総額が3,000万円の場合、
- 建物:1,200万円
- 土地:3,000万円 − 1,200万円 = 1,800万円
建物価格を「概算」で推定できるため、固定資産税評価額が入手できないときに有効です。土地の価額については、全体の価額から建物の価額を差し引いた価額です。その価額は必ずしも「合理的」と言えない事もあり、否認されるケースもあります。
③ 土地の路線価や公示価格を基準に計算する方法
土地の評価を先に算出し、残余を建物とみなす方法です。
例
- 土地面積:150㎡
- 路線価:1㎡あたり12万円
- 土地価額:150㎡ × 12万円÷0.8 = 2,250万円
売買契約書の総額が3,000万円の場合、
- 土地:2,250万円
- 建物:3,000万円 − 2,250万円 = 750万円
土地の価値を基準に算定できるため、路線価が明確に出ている都市部で利用しやすい方法です。相続税評価で用いる「路線価」は、その時の相場の約80%程度とされています。よって路線価の金額を80%で割り戻した金額を土地の価額とします。
こちらの方法は建物の価額を差し引きで概算で計算していますので、その建物の価額は必ずしも「合理的」と言えない時もあります。
④ 鑑定評価を利用する方法
不動産鑑定士に依頼して「土地と建物の鑑定評価額」を出してもらい、その比率で按分する方法もあります。特に高額不動産や、将来の税務リスクを避けたい場合に選ばれることがあります。
例:
- 売買代金(合計):2億円
- 鑑定評価(土地):1億4,000万円
- 鑑定評価(建物):6,000万円
→ 土地:2億円 × (1.4億 ÷ 2.0億) = 1億4,000万円
→ 建物:2億円 × (0.6億 ÷ 2.0億) = 6,000万円
この場合は鑑定書があるため、税務署に対しても強い合理性を示すことができます。ただし、不動産鑑定士に不動産評価の鑑定を依頼する時は数十万円のコストが生じます。
実務上の注意点
① 契約書に内訳を記載してもらうのがベスト
後で揉めないよう、売買契約書に土地・建物の金額を明示してもらうのが基本です。
② 内訳がない場合は「合理的に」按分する
固定資産税評価額、路線価の割戻し、鑑定評価のいずれかを使いましょう。固定資産税評価額は実務上一番使われている手法で合理的と言われます。また、鑑定評価は「時価との整合性」が高いため有効です。
③ 税務調査で否認される可能性を考える
どのような評価方法で内訳を計算しても、建物の価額を多く見積もって償却を増やすような操作は、税務署から「不自然」と見られます。評価根拠を明確に残しておくことが重要です。例えば、固定資産税の評価額は土地の方が高いのに、按分した後の価額は建物の価額の方が高い場合だと不自然に見られたりします。
まとめ
土地建物一括取引の場合でも、税務・会計実務では必ず「土地の価額」「建物の価額」に内訳を分ける必要があります。
実務上、重要なのは「評価の根拠をきちんと残すこと」です。評価の根拠が「合理的」であるかは、ケースバイケースです。税理士などの専門家に相談をしながら、計算する事をお勧めします。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
不動産に関する税務は多岐に渡り、税制改正が多いのも特徴です。
税理士法人Accompanyでは、税制改正に対応した税務サービス、節税提案をはじめとした『会計税務顧問サービス』をおこなっています。
また、不動産に関する会計は取引が複雑なこともあり、会計帳簿の作成の難易度が高いです。
日々の会計帳簿の作成に困っている企業様も多いかと思います。弊社では会計処理のお手伝いのサービスも行っております。
「不動産業におけるインボイス対応」も含め、不動産に関する会計・税務にお悩みの方は、ぜひ一度、ご相談頂けたら幸いです(初回相談は無料)。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
\24時間365日受付中 /
『会計税務顧問サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。