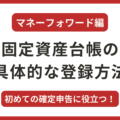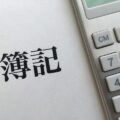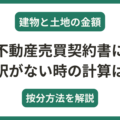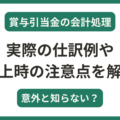こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
会社として香典を出すことは、取引先や従業員への弔意を示す大切な慣行です。
しかし、誰に対する香典かによって税務上の扱いが大きく異なる点に注意が必要です。
結論からいえば、従業員やその親族に対する香典は「福利厚生費」として扱われ、取引先など事業関係者に対する香典は「交際費」として扱われます。この区分を誤ると、税務調査で「損金算入できない」と指摘されるケースもあります。
本記事では、香典の支出に関する税務上の取扱いを整理し、実務での対応方法を解説するとともに香典っていくらくらい出すものなのという疑問にもお答えしようと思います。
目次
香典の基本(従業員向け or 取引先向け)
従業員・その親族への香典
従業員本人やその家族の不幸に際して支給される香典は、原則として福利厚生費として損金算入可能です。ただし、ここで重要なのは、一定の基準に従って一律に支給していることです。
例えば次のような基準が必要です。
- 社員本人の葬儀:3万円
- 配偶者:2万円
- 父母:1万円
このように明確な支給基準を定め、全社員に公平に適用していることが求められます。
この基準が曖昧だったり、特定の社員だけ高額だったりすると、福利厚生費ではなく「給与」として課税対象になるリスクが生じます。
取引先・顧客など事業関係者への香典
一方、取引先や顧客などの葬儀に対する香典は、交際費等として扱われます。
交際費は法人税法上、原則として損金不算入の対象ですが、中小法人(資本金1億円以下等要件あり)には一部損金算入となる特別な措置があります。
いくらまで経費にできる?
従業員向け(福利厚生費)
福利厚生費としての香典には、明確な上限額は定められていません。
大切なのは、支給基準が社内規程などで明文化されているかどうかです。
また、過度に高額な支給は、実態として「給与」とみなされる可能性があり、税務上否認されるリスクがあります。
ポイント
- 支給基準は就業規則・慶弔規程で定める
- 支給金額・続柄・支給日を記録する
- 領収書や決裁記録を保存しておく
取引先等への香典(交際費扱い)
交際費等は原則として損金不算入です。(法人税を計算する際に経費にできないという意味です。) 資本金1億円以下の法人では、次のいずれか少ない方まで損金算入できます。
- 年間800万円まで
- 飲食費のうち50%まで
つまり、取引先への香典もこの「交際費等の枠」に含まれるため、年間の交際費等の合計が800万円以内であれば、実質的には損金算入可能です。(事業年度が12か月の場合、800万円が上限)
実務での対応ポイント
慶弔規定(社内ルール)を整備する
慶弔規程には、次の内容を明文化しておくとよいでしょう。
- 対象者(社員・家族・元社員など)
- 支給金額の基準(本人3万円、配偶者2万円など)
- 稟議・支給方法・決裁方法
この明文化された慶弔規定が、税務調査で福利厚生費と認められるかどうかの判断基準になります。
証拠書類を残す
香典の支払いについては、以下のような資料を整備・保存しておきましょう。
- 支払伝票(支出目的・金額・支払日・受取人の続柄)
- 領収書や振込明細
- 社内承認(稟議書)・決裁記録(決裁書)
さらに、勘定科目(福利厚生費・交際費)を明確に区分し、会計処理を統一しておくことが重要です。
高額な場合は事前に税理士へ相談
香典の金額が一般的な相場を超える場合や、代表者個人の知人関係など業務外の支出に該当する場合は、損金不算入の可能性が高まります。
そのようなケースは、事前に顧問契約のある税理士へ相談しておくことをお勧めします。
よくあるケースと判断例
よくあるケースと判断の例をいくつかご紹介します。
ポイント
| ケース | 区分 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 社員の親の葬儀に会社が2万円支給 | 福利厚生費 | 一律基準に基づく支給であれば損金算入可 |
| 取引先社長の葬儀に3万円の香典を支出 | 交際費 | 交際費枠(800万円以内)で損金算入可 |
| 代表者の友人の葬儀に10万円を支出 | 個人支出 | 会社経費にできない(損金不算入) |
まとめ:明確なルールと記録が節税のカギ
香典は気持ちで支出をするものですが、税務上は誰に・どのような基準で支給したかが重要になります。同じ香典でも、従業員向けなら福利厚生費・取引先向けなら交際費と区分が異なりますし、損金算入の可否も変わります。
ルールを明文化し、支払の証拠を残すことで、税務調査時にも安心して説明ができます。
迷う場合は、必ず税理士へ相談しましょう。
参考リンク(国税庁)
香典に関連する国税庁のリンク先は以下のとおりです。
No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(国税庁)
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
No.5389 社葬費用の取扱い(国税庁)
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm
参考 香典の実態調査
実態調査をしましたが、公にはされておらず、いくつかの企業が参考に公表しているものを分析しました。
そこから大まかな支出の範囲を支出先別に示すとおおよそ次の範囲となります。(当社調べ)
- 取引先 平均3万円(1万円~10万円の範囲)
- 社内従業員 平均10万円(ただし、勤務年数による幅が大きく5千円程度~数十万円程度まで差が大きく企業の規模によっても差が大きい印象です。)
- 社内従業員の親族 平均1万5千円(5千円~5万円の範囲)
香典の支出額を公開している企業のサイト情報などを参考にして調べたものですが、企業により支出額に差がある印象でした。
あくまで、参考に止めておいていただき、自社に合った慶弔規定を作成することをお勧めします。
最後に

参考になりましたでしょうか。
結論:原則として「社内慶弔規定」を作成することが重要です。
社内規定は、法律で作成を強制されているものではありません。
ただし、①恣意的な支出、②役員だけに支給するなどの不平等、③私的流用を抑制することなどを考慮すると社内規定を設けておくことが必須だと思います。
是非参考にされてみてください。
自社の経理をご自身で行っておられる経営者の方へ
弊社は
- 記帳代行のみのご依頼
- 月次顧問のご依頼
- 年1回の決算/確定申告のご依頼
などのサービスを行っている顧問先数700社超、クラウド会計導入実績300社超の税理士法人です。
- より効率的な自計化を進めたい
- 利益が出ているはずなのにキャッシュが減っており原因が分からない
- クラウド会計を導入して事務負担を軽減したい
など、お客様に寄り添ったサービスの提供が可能です。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
初回のご相談は無料ですので、会計や税務・経営に関するお悩みがある方はお気軽にご相談ください。
\24時間365日受付中 /
『確定申告サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。