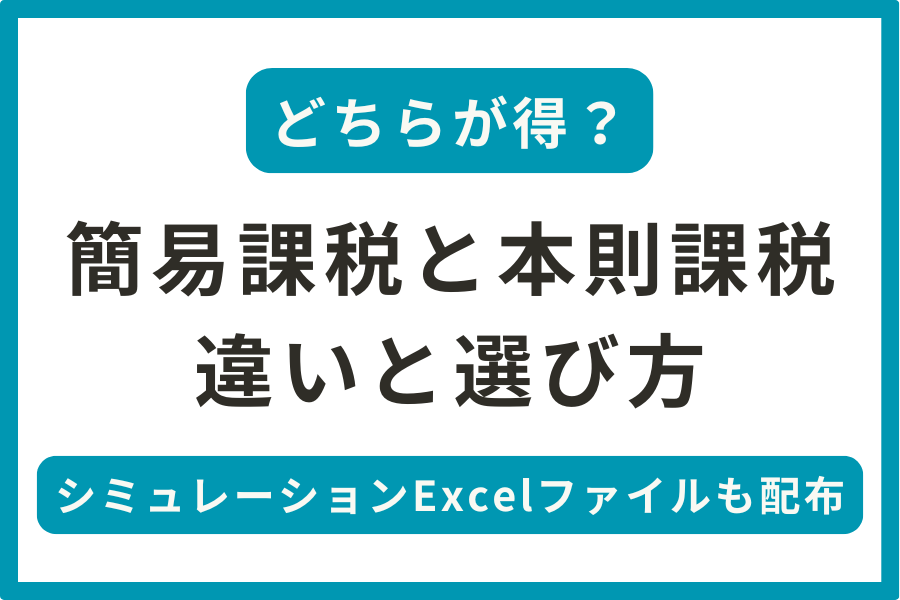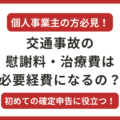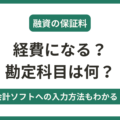こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
令和5年10月1日より開始された、「インボイス制度」のスタートにあわせて、もともと免税事業者だった方が新たにインボイス発行事業者になった場合の負担をやわらげるために、「2割特例」という仕組みが設けられました。
この特例を使うと、本来の複雑な消費税の計算をせずに、「売上にかかる消費税の2割だけを納税すればよい」という、シンプルで簡便な方法で申告・納税ができます。
実務の負担を軽くしつつ、消費税の納税額も一定程度抑えられるため、多くの小規模事業者にとって助けになっていた制度です。
しかしこの2割特例はあくまで時限的な経過措置であり、令和8年9月30日で終了することが決まっています。
この記事では、この2割特例の内容と、終了後にどう変わるのか・今から何を準備しておくべきかを整理していきます。
2割特例とは
本来、課税事業者となった場合、消費税納付額は
「売上に係る消費税額-仕入れ等に係る控除対象消費税額」
で計算します。
しかしこの「2割特例」は、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合に、
「売上に係る消費税額の2割を納税額とする」
ことで、仕入控除税額の算定を省略し、事務負担や税負担を軽減するものです。
2割特例の適用期間について
この2割特例を適用できる課税期間は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」となっています。
つまり、もうすぐ2割特例を適用できる期間が終了することになります。
この適用期間終了の考え方について、法人・個人それぞれで確認をしていきましょう。
法人の場合
法人の場合、令和8年9月30日の属する課税期間までで適用が終了となります。
決算日ごとに例をあげると下記のようになります。
例1)3月末決算の場合
令和8年3月決算分:2割特例適用可能
令和9年3月決算分:2割特例適用可能(令和8年9月30日を含むため)
令和10年3月決算分:2割特例適用不可
例2)8月末決算の場合
令和8年8月決算分:2割特例適用可能
令和9年8月決算分:2割特例適用可能(令和8年9月30日を含むため)
令和10年8月決算分:2割特例適用不可
例3)9月決算の場合
令和8年9月決算分:2割特例適用可能
令和9年9月決算分:2割特例適用不可(令和8年9月30日を含まないため)
「令和8年9月30日を含む期間かどうか」ということになりますので、自社の決算日の場合、いつまで適用ができるのかを確認しておきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、令和8年9月30日までの属する課税期間までで適用が終了となるため、令和8年分の確定申告までは2割特例を適用することができます。
令和8年分:2割特例適用可能(令和8年9月30日を含むため)
令和9年分:2割特例適用不可
対応すべきポイント
終了後は、2割特例を選択できなくなるため、課税事業者となった後の消費税負担が変わることを前提にしておく必要があります。
消費税の計算方法の選択
終了後は、インボイス登録を継続して、引き続き課税事業者である限り、本則課税(原則課税)か簡易課税かを選ぶしかありません。
2割特例があるため、本則課税を選択していた方も多いかと思いますので、ここであらためて本則課税か簡易課税の有利な方を判定する必要がでてきます。
本則課税か簡易課税かの計算方法についてはこちらで詳細に説明をしています。
どちらが有利かを判定できるシミュレーションシートもありますので、ぜひご活用ください。
計算の結果、本則課税(原則課税)が有利になった場合は、特に届出等の必要はないので、申告時に原則課税で計算・申告を行えば大丈夫です。
計算の結果、簡易課税が有利になった場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
簡易課税を選択する場合の届け出について
通常、簡易課税制度を適用したい場合は、その「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に、納税地の所轄税務署長あてに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、2割特例を受けていた事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度を選びたい旨の届出をした場合には、その届出書を「当該課税期間の末日まで」に提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられる扱いとなっています。
例1)3月末決算法人の場合
令和9年3月決算分:2割特例適用
令和10年3月決算分:2割特例適用不可
令和10年3月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば
この年度分から簡易課税を適用することができる
例2)個人事業主の場合
令和8年分:2割特例適用
令和9年分:2割特例適用不可
令和9年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば
令和9年分から簡易課税を適用することができる
前年度末までに判定ができていなかった場合でも簡易課税の選択が間に合うことになります。
また、1年間どちらを選択するかの猶予がもてることになるので、本則課税と簡易課税のどちらが有利かの判断に迷う場合は、期末までの動きを見て決められるということになります。
※この特例はあくまで「2割特例を適用していた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度を選択する場合」に限られるものです。
通常の事業者が簡易課税を選びたい場合や、2割特例を適用していた課税期間の翌々期間以降は、前述の「課税期間開始前日まで」の原則が適用されますので注意しましょう、
帳簿・仕入税額控除の準備
本則課税を選択した場合、仕入れ等に係る控除対象消費税額を把握する必要があります。
その場合、軽減税率・インボイス未登録事業者からの仕入れなど、支払った際の消費税区分について1つずつ判断して記帳していくことになります。
また、仕入れ側の消費税額控除を適切に行うためには帳簿記録・保存書類の準備が必要です。
区分をしっかりしないと納税額の負担が増加する可能性もありますので、帳簿記録や書類の保存などをしっかりして消費税区分を正しいものにしていくことが重要になります。
まとめ
この「2割特例」は、免税事業者がインボイス発行事業者となった際の 短期的な支援措置 であり、永久的な制度ではありません。
法人・個人を問わず、令和8年9月30日をひとつの区切りと考え、残りの期間で「終了後どうするか」を検討しておくことが重要です。
特に、簡易課税制度を選びたい場合は、期首から適用できる特例的な届出期限(期末までOKの措置)もありますので、慌てず正しいタイミングで手続きできるようにしましょう。
実際には、売上規模や取引先の状況によって本則課税か簡易課税かの有利・不利が変わることも多いです。
どちらを選択したらいいか迷ったときは、ぜひ早めにご相談ください。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。