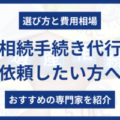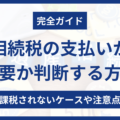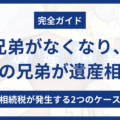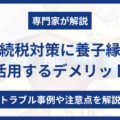相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
結論としては、基本的に税理士費用を払う人は決められておらず、誰が払っても問題ありません。
しかし、「一般的に配偶者が払うことがよい」とされています。
この記事では、
・相続の税理士費用は、配偶者が払うことがよい理由
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説します。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
また、相続の際には、トラブルが発生しがちであることにも留意しなければなりません。
できればトラブルが起こる前、生前にできるだけの対策をしておくことが、後々のトラブルを防止する鍵となるでしょう。
その点を考慮しても、相続トラブルを防ぐためには、税理士への相続対策相談がおすすめです。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
目次
相続の税理士費用が誰は払うのがベストか
相続税申告を税理士に複数人で依頼したとき、税理士費用は誰が払うのか問題になる可能性があります。
税理士費用を誰が支払うのかは規定がなく、1人が全額を支払う、全員で均等に負担するなど、支払い方は自由です。
しかし、実際には配偶者が全額支払うことがよいとされています。
相続の税理士費用は配偶者が払うのがよい理由
ではなぜ、税理士費用は配偶者が全額負担するのがよいのでしょうか。
その理由について解説します。
税理士費用は控除されない
相続税を算出するときはさまざまな控除があり、支払うべき相続税を軽減できます。
しかし、税理士費用に関する控除はなく、誰が支払っても節税対策とはなりません。
配偶者の法定相続分は2分の1と、相続人のなかで一番多いことから、税理士費用も配偶者がまとめて支払うケースが多くみられます。
「配偶者の税額軽減」がある
配偶者が相続する財産が一番多いだけではなく、配偶者だけが受けられる税額軽減も存在します。
配偶者の場合、相続する財産の金額が1億6,000万円までならば相続税は発生しません。
そのため、子や親のほうが相続する金額が少ないのに、配偶者よりも多く相続税を支払うようなことも起こりえます。
そういった負担額の差があることも、配偶者が税理士費用を負担すべき理由の1つとなっています。
二次相続を考慮する
二次相続とは、「配偶者がすでに亡くなっている人」が亡くなったときに発生する相続で、配偶者に相続できる財産がない状態のことです。
配偶者がいなければ「配偶者の税額軽減」は利用できず、全体的にみると支払う相続税の金額が大きくなってしまいます。
このような事態を避けるためには、配偶者がすでに亡くなっている人が税理士費用を支払い、少しでも二次相続の額を減らすことも必要です。
配偶者の税額軽減の注意点
税理士費用を配偶者が支払う理由の1つである税額軽減ですが、この軽減を受けるためには注意点があります。
内縁関係や事実婚には適用されない
配偶者の税額軽減は法律上の配偶者に限られます。
内縁関係や事実婚、婚約中の相手は、配偶者の税額軽減は利用できず、遺言等で相続したとしても通常の相続税を支払う必要があります。
亡くなったあとに婚姻関係は結べず、亡くなった時点で法律上の婚姻関係になければなりません。
別居・離婚調停中は適用される
別居や離婚調停中などで実際は夫婦としての関係は終了したとしても、離婚届が受理されていなければ、配偶者として遺産を相続可能です。
法律上の婚姻関係があれば、配偶者の税額軽減を利用できます。
相続人としての配偶者がいない場合
配偶者がいる場合、税理士費用は配偶者が支払ったほうがよいとされていますが、二次相続や独身者が亡くなったときなどは、配偶者はいません。
配偶者がいない相続のときの税理士費用は、それぞれが共同で税理士費用を負担することが一般的です。
相続した額に応じて税理士費用も分配するようにすれば、不公平感も起きにくいでしょう。
相続における税理士費用の目安
相続にかかる税理士費用はいくらくらいなのか、その目安について解説します。
税理士費用の相場は遺産総額の1%程度
税理士費用は依頼する税理士によっても異なりますが、目安としては遺産総額の1%程度です。
こちらはあくまで「基本報酬」の目安であり、実際はそれよりも多くなることもあります。
遺産総額が大きい、相続する人が多い、遺言があり相続が複雑など、相続税の計算が難しくなるような事情があると、その分税理士費用も増えるでしょう。
オプション費用が発生する場合がある
相続税算出における税理士費用では、基本報酬にくわえ加算報酬としてオプション費用が発生する可能性があります。
どのような事柄がオプション費用発生の原因となるのか紹介します。
相続財産に土地が含まれる場合
相続税を算出するときには、相続財産を金額として評価しなければなりません。
土地は立地、広さ、そのときの経済情勢などによって評価額が変わるため、評価には時間がかかります。場合によっては現地調査が必要で、税理士の出張手当や交通費がかかることもあるでしょう。
そのため、相続財産に複数の土地が含まれているときはオプション費用がかかる可能性があります。
非上場の株式がある場合
非上場の株式は市場に出ていないことから、現在の評価額を客観的に評価しにくい性質があります。
該当する企業の総資産、利益、負債などを総合的に評価し、現在の評価額を算出しなくてはなりません。非上場株式がある場合、1社あたりの加算報酬を設定している事務所もあります。
相続人が多い場合
相続税の算出は相続人が多いほど複雑になります。そのため、相続人の数に応じてオプション費用として加算報酬を請求される場合もあります。
何人から加算報酬となるのかは税理士事務所によっても異なるため、依頼前に料金を確認しておくとよいでしょう。遺言により法律で定められている人以外にも相続がある場合は要注意です。
申告期限まで残り少ない場合
相続税には被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内という申告期限があります。
これを過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる可能性があるため、期限内に申告を終わらせなければなりません。そのため、申告期限まで残り少ない場合は税理士の負担は増えてしまいます。
税理士事務所にもよりますが、残り3ヶ月を切ると加算報酬が発生する傾向にあるため、早めに依頼しましょう。
準確定申告を行うことが必要な場合
準確定申告とは、生前確定申告をすべき収入があった人が亡くなったときに行う確定申告です。相続人が所得金額、税額を計算し、相続を開始したこと知った日から4ヶ月以内に相続税の算出とともに、準確定申告を行わなければなりません。
準確定申告を依頼するのであれば、これに対する加算報酬が発生することが一般的です。
書面添付制度を利用する場合
書面添付制度とは、税理士が申告書の内容が正しいことを証明する書面を添付できる制度です。これにより、申告書の信頼性が上がり税務調査が省略される、申告漏れがあっても罰金が課されない、といったメリットを受けられます。
この制度を利用し、税理士に書面を添付してもらうときには加算報酬が発生するケースが多いでしょう。
相続の際に依頼する税理士を選ぶ4つのポイント
税理士は報酬や手法もさまざまで、選び方に失敗することもあります。
そこで、税理士選びに失敗しないための4つのポイントについて解説します。
料金が明確である
ホームページなどで、税理士報酬である料金を明確に公開している税理士事務所は信頼性が高いでしょう。
料金があらかじめ提示されていない場合、着手後に想像よりも高い報酬を請求され、トラブルに発展する可能性もあります。
依頼前にどのくらいの税理士報酬がかかるのか確認できる税理士事務所のほうが安心です。
成功報酬型の料金体系には注意する
成功報酬型とは、節税に成功したときにその分に応じて報酬が決められるものです。
成功報酬型で税理士報酬を受け取ることは違法ではありませんが、結果として通常の税理士報酬よりも高くなる可能性もあります。
また、通常の業務として当たり前に節税対策をしている税理士事務所もあることから、成功報酬型の税理士事務所には注意が必要です。
相続の実績がある
ひとことに税理士と言っても、扱う分野は相続以外にもさまざまです。
そのため、税理士にもそれぞれ得意不得意な分野はあります。
相続税について税理士に依頼するのであれば、相続の実績が多く、相続が得意な税理士を選んだほうがよいでしょう。
ホームページなどで実績を公開している人もいるため、それを参照してみてください。
税務調査について確認する
税務調査とは、申告した内容に疑いがあるため、税務署が改めて申告内容を調査することです。
税務調査が入り申告漏れやミスが発見されると、過少申告加算税や重加算税、延滞税などが加算される可能性があります。
そこで、依頼前にその事務所の税務調査率や、もし税務調査が入ったときのノウハウがあるかどうかは確認しておいたほうがよいでしょう。
また、書面添付制度を導入していて、税務調査が入る可能性を低くする取り組みをしている事務所を選ぶこともおすすめです。
まとめ
相続税について税理士に依頼したときは、すべて配偶者が税理士費用を払うほうがよいとされています。
これには、配偶者は税額軽減を受けられること、二次相続の際に残っている相続財産を減らすことが理由です。
配偶者がいない場合は相続した額に応じて、相続人全員で税理士費用を負担すると、トラブルは起きにくいでしょう。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
また、相続の際には、トラブルが発生しがちであることにも留意しなければなりません。
できればトラブルが起こる前、生前にできるだけの対策をしておくことが、後々のトラブルを防止する鍵となるでしょう。
その点を考慮しても、相続トラブルを防ぐためには、税理士への相続対策相談がおすすめです。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。