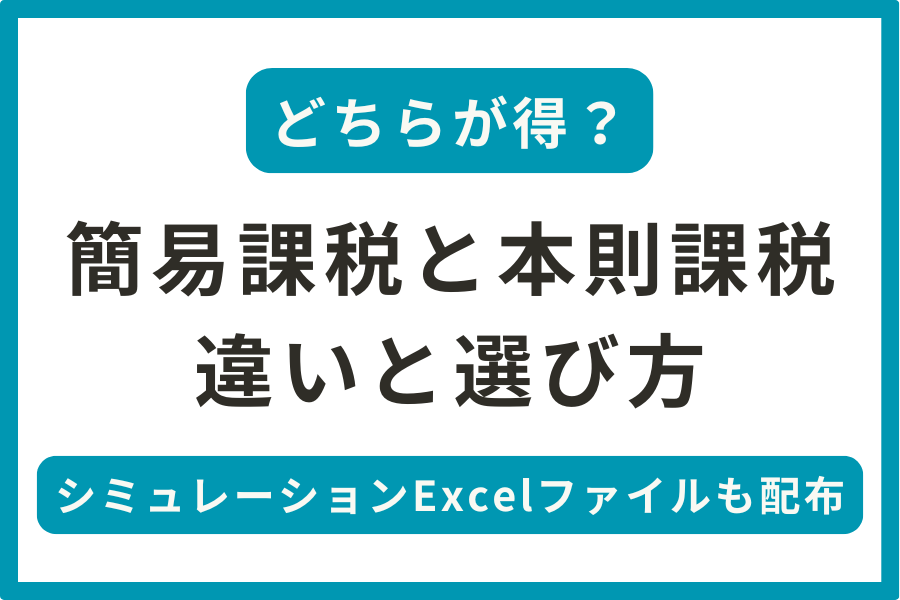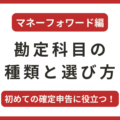「1枚の領収書に消費税率が10%のものと軽減税率8%のものが混在している場合、どのように仕訳を入力すればいいの?」という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
今回は、このようなケースでの仕訳方法について、わかりやすく解説します。
(本文では、軽減税率8%のことを「軽減8%」と表記しております。)
消費税区分を分ける必要があるか?
1枚の領収書に消費税率が複数混在している場合、消費税区分を分けるべきかどうかがまず疑問にあがるのではないかと思います。
消費税区分を分けるべきかどうかは、事業者の課税方式によって異なります。
分けた方がよい人
課税事業者で本則課税を採用している場合
本則課税を採用している場合は、売上で受け取った消費税から経費等で支払った消費税を差し引いて納付を行うため、経費等で支払った消費税がいくらあるかをきちんと計算する必要があります。
10%と軽減8%の税率ごとに消費税を計算する必要があるため、仕訳を分けるのが基本です。
分けなくてもよい人
免税事業者の場合
免税事業者の場合は、 そもそも消費税の申告義務がないため、消費税区分を分ける必要はありません。
簡易課税制度を適用している場合
簡易課税制度を採用している場合、売上で受け取った消費税額をもとに消費税の納税額の計算を行うため、消費税区分を厳密に分けなくても問題ありません。

免税事業者でインボイス登録を行っていて2割特例の適用対象になる方や、簡易課税を採用している方あれば分けなくても大丈夫です。
本則課税を採用している場合は分けて入力するのがおすすめです!
2割特例と本則課税の税額が少ない方を選択することができます。
分けなかった場合のリスク
消費税区分を分けなかった場合、以下のようなリスクが考えられます。
1.消費税の申告誤りによる追徴課税のリスク
対象:本則課税の課税事業者
軽減8%のものを10%で処理すると、控除額が過大になり、消費税の納税額が少なくなるため、税務調査で指摘を受けた場合、追加の消費税・延滞税を支払う可能性があります。
2.仕入税額控除が正しく受けられない
たとえば10%で処理すべきものを軽減8%で処理してしまうと、本来控除できる消費税の額が少なくなってしまいます。
本来軽減8%の仕入税額控除と10%の仕入税額控除を分けて処理すべきところを一括で処理してしまうと、税務申告時に適切な控除が受けられず、結果として余分な税金を支払うことになりかねません。
消費税を分けて入力する場合の仕訳の方法
1枚の領収書に10%のものと軽減8%のものが含まれている場合、それぞれの金額を分けて仕訳を行います。
仕訳方法の例
【例】事務用品(消費税10%):5,500円(税抜5,000円、消費税500円)と
会議用の飲料(軽減税率8%):2,160円(税抜2,000円、消費税160円)を一緒に買って
レシートの合計金額が7,660円の場合
| 事務用品費 | 5,500円 (課税仕入10%) | 現金 | 7,660円 |
| 会議費 | 2,160円 (課税仕入8%(軽)) |
仕訳時の注意点
- 仕訳を行う際は、税率ごとに適切な税区分を設定する。
- 事業の経費科目ごとに正しく分類することで、正確な会計処理が可能になる。
まとめ
1枚の領収書に異なる税率が含まれている場合は、事業者の課税方式によって、仕訳の方法が異なります。
- 本則課税の課税事業者は、消費税率ごとに分けるのが望ましい。
- 免税事業者や簡易課税事業者は、分けなくても問題はない
適切な仕訳を行うことで、消費税の計算ミスを防ぎ、スムーズな会計処理が可能になります。日々の経理業務の参考にしていただければ幸いです!

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。