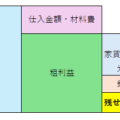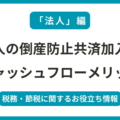こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
これまで300社の中小企業を税理士として融資をサポートしてきました。
中小企業でほとんどの企業が融資を活用しています。その融資の際によく出る言葉であるEBITDA(償却前利益)です。この記事では
- EBITDA(償却前利益)の意味
- EBITDA(償却前利益)の計算方法
- 銀行のEBITDA(償却前利益)の活用方法
- EBITDA(償却前利益)のメリット・デメリット
具体的な数値例とともにご紹介します。
EBITDA(償却前利益)の意味
EBITDA(償却前利益)とは「Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization」の略で、「利息・税金・減価償却前の利益」を意味します。
言い換えると、企業の「本業の営業活動でどれだけお金を稼いでいるか(キャッシュ創出力)」を示す指標です。
EBITDA(償却前利益)の計算方法
EBITDA(償却前利益)は会社の損益計算書に記載されている数字を使って計算します。
計算方法は以下のようになります。
EBITDA(償却前利益) = 営業利益 + 減価償却費
または
EBITDA(償却前利益) = 税引前当期純利益 + 支払利息 + 法人税等 + 減価償却費
銀行は企業に貸し出した資金を「きちんと返せるか?」を最も気にします。 この時、当期純利益よりも「実際のキャッシュフローに近い数値」であるEBITDA(償却前利益)が重視されるのです。
利益が出ていてもキャッシュがなければ返済は不可能だからです。
具体的な計算例は以下のようになります。
- 当期純利益:1,200万円
- 支払利息:300万円
- 法人税等:500万円
- 減価償却費:1,000万円
このときのEBITDAは
→ 1,200 + 300 + 500 + 1,000 = 3,000万円
企業の年間借入返済額が4,000万円であれば、
→ EBITDA(3,000万円)< 返済額(4,000万円)
となり、銀行は「返済能力が不足」と判断するかもしれません。
逆に、返済額が2,000万円であれば、
→ EBITDA(3,000万円)> 返済額(2,000万円)
となり、銀行から「十分返済できる」と評価されやすくなります
銀行のEBITDA(償却前利益)の活用方法
銀行は、以下のような場面でEBITDA(償却前利益)を実務に使っています。中小企業は⑴や⑵のケースの際によく活用されています。
融資審査時の「返済余力」の確認
融資審査では、企業が本当に返済できるかをEBITDAを用いて検証します。
特に「EBITDA ÷ 年間借入返済額」の倍率を重視し、1.5〜2倍以上あれば「返済に余裕あり」と判断されることが多いです。
融資後の期中モニタリング
融資実行後も、銀行は毎期の決算書をチェックして返済能力を定点観測します。
このとき、単なる売上や利益だけでなく、EBITDAの水準や推移から企業のキャッシュ体質の変化を把握します。
リスケ・企業再生時の基準として
返済条件の見直しやリスケを検討する際にもEBITDAは重要です。
たとえ赤字決算でも、EBITDA(償却前利益)がプラスであれば「キャッシュで返済できる余地がある」として支援が可能になります。
M&A・事業承継での企業価値評価
EBITDA(償却前利益)は、M&Aや事業承継時の企業評価にも使われます。
例えば、「EBITDA(償却前利益)の5倍で企業価値を算出する」など、業界ごとの相場に基づいて価値を見積もる際の基礎数値になります。
EBITDA(償却前利益)のメリット・デメリット
EBITDA(償却前利益)を活用する際のメリット・デメリットは以下のようになります。
メリット
- キャッシュ創出力が見える
減価償却などの“帳簿上の費用”を除くため、資金繰りとの整合性がある。 - 会計処理の差異を除外できる
利息・税などの影響を除外し、「本業の稼ぐ力」を測れる。 - 借入金の返済能力を判断しやすい
EBITDA ≧ 年間返済額 であれば銀行も安心して融資できる。
デメリット
- キャッシュの純増ではない
設備投資や運転資金の変動は考慮されていない。 - 一時的な利益でも増加する
継続性のない収益が含まれる可能性もある。 - フリーキャッシュフローとは別物
EBITDAは営業活動ベース。実際のキャッシュ残高の動きは別途分析が必要。
まとめ
- EBITDA(償却前利益)は、企業が「キャッシュをどれだけ生み出しているか」の目安となる指標
- 特に銀行は、EBITDA(償却前利益)を用いて「借入金の返済余力」を判断しており、融資審査やリスケ判断、M&Aの企業価値算定などにも活用しています。
- 単なる会計上の利益ではなく、キャッシュベースの経営力を把握することが、経営の安定にもつながります。
「自社のEBITDAが妥当なのか分からない」「返済計画に不安がある」「銀行にどう説明すればいいか悩んでいる」といった場合は、数字に強い税理士に相談するのも良いでしょう。
財務の見える化と戦略的な資金繰り改善は、経営にとって大きな武器になります。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。