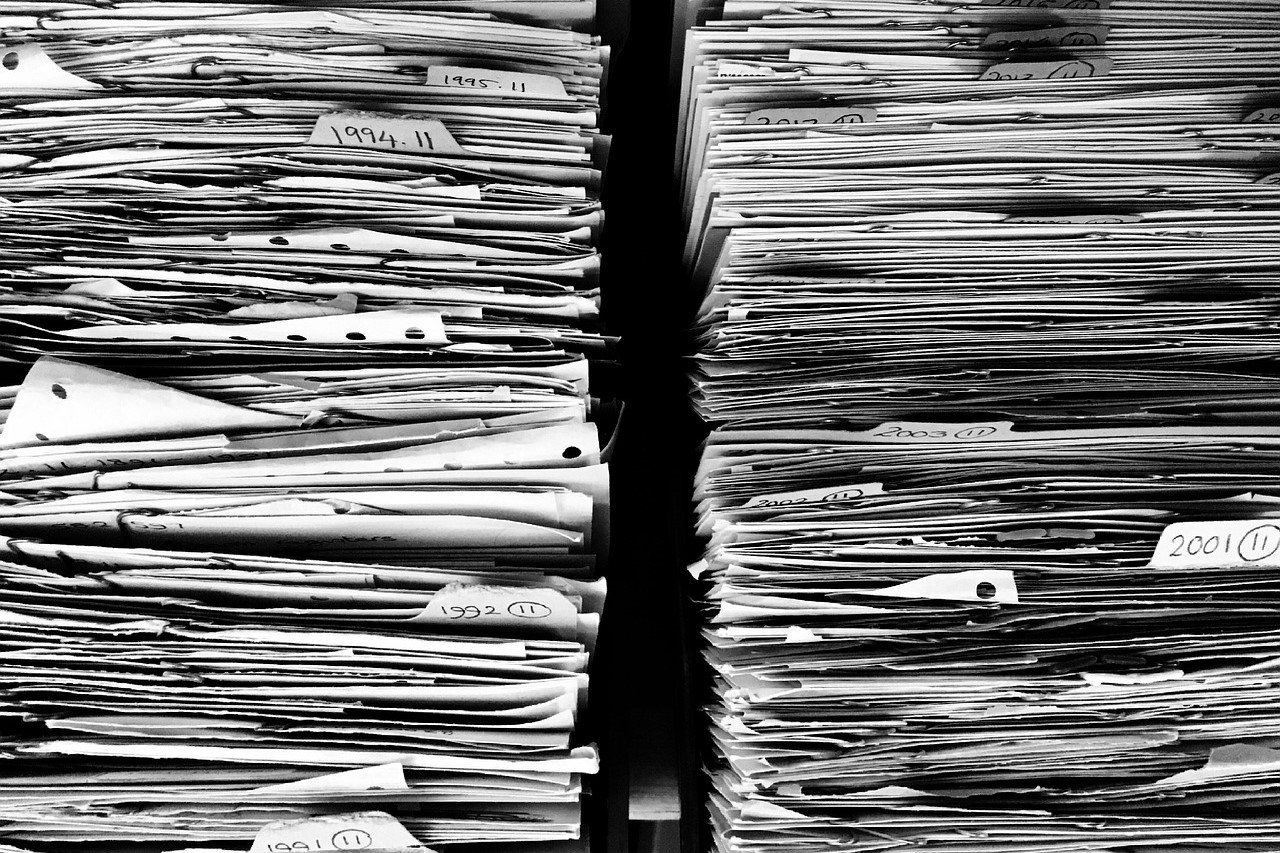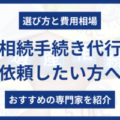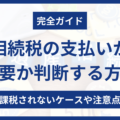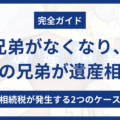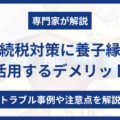遺産相続により不動産を相続すれば、相続登記を行うのが通常です。
相続登記をせずに放置するとデメリットが発生します。
相続登記の義務化も予定されているため、不動産を相続した相続登記を済ませておくことが無難です。(令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。)
今回は、相続登記の方法や必要書類などについて解説します。
不動産の相続を予定されている人は参考にしてくださいね。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続の場合は、相続税を始めとして複雑な手続きが多いため、税理士事務所が相続に関する一切を代行するケースも増えています。
また、相続財産が決して多いというわけでなくても、相続トラブルが発生しがちであることにも留意しなければなりません。
できればトラブルが起こる前、生前にできるだけの対策をしておくことが、後々のトラブルを防止する鍵となるでしょう。
相続トラブルを防ぐためには、税理士への相続対策相談がおすすめです。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
目次
相続登記とは何か?
相続登記とは、相続で不動産を所有した場合に、被相続人から相続人へと名義変更するための手続きです。
法務局では、管理する登記簿に、土地や建物に関して所有者が誰であるかなどの情報を記録しています。
これにより、不動産の権利が明らかになります。相続登記を済ませることで、第三者に対して不動産の権利を明確に示すことが可能です。
相続登記をせずに放置した際のデメリットとは
相続登記をしなくても、現在のところ罰則はありません。
しかし、相続登記をせず放置した際にはデメリットが発生します。
この章で具体的な内容を確認しましょう。
遺産分割協議が滞る
遺産分割協議とは、被相続人の遺産の分割を、相続人全員で協議することです。
相続登記せずに放置されていた不動産の遺産分割協議は、時間が経つほど次の相続が発生して相続人が増えているため、遺産分割協議が滞りがちになります。
未登記不動産であっても、相続人は登記申請義務があります。
不動産の賃貸と売却ができない
相続した不動産を貸し出したり売却したりする場合は、不動産登記を済ませておく必要があります。
名義人本人でなければ、不動産の賃貸契約や売買契約はできません。
相続登記を放置して時間が経っている場合は、相続人が増えて不動産の権利関係が複雑になり、通常よりも相続登記に時間がかかる場合もあります。
相続する不動産が差し押さえられる恐れがある
相続登記を済ませておかなければ、相続する不動産が第三者に抑えられる可能性があります。
相続人の誰かに借金があれば、その債権者は遺産分割協議と相続登記が完了していない間に、不動産を差し押さえることができるため注意が必要です。
令和6年に相続登記の義務化が予定されている
先に少し触れましたが、相続登記の義務化に関する法律が令和3年4月に可決成立しました。
法律の施行日は令和6年4月1日と定められています。
法律が施行されると、相続により取得することを知ってから3年以内に、相続登記申請が義務付けられます。
違反者には10万円以下の過料が課されるため、不動産を相続したら、早期に相続登記を済ませましょう。
この法律は、相続の発生が法律の施行前後に関わらず、すべての相続について適用があります。
つまり、改正法施行前の相続に対しても、過料が課される可能性があります。
相続登記を行う手順とは
相続登記を行う際には手順があります。
ここでは、必要な手順について解説します。
相続される不動産を把握する
相続登記を行うにあたって、相続対象の不動産の把握が大事です。
まずは、不動産の状態や権利関係などを確認しましょう。
不動産の現物や登記事項証明書などで現状を確認します。
不動産は土地と建物が分かれて登記されているため、それぞれの所有者を確認してください。
土地を分割所有している場合には、被相続人が所有していた土地のみが相続の対象です。
相続する人を決める
遺産相続においては、被相続人の意思でもある遺言書が優先されます。
遺言書で不動産の相続人が指名されている場合は、被相続人の意思通りに相続するのが一般的です。
遺言書がないときは、遺産分割協議で不動産を誰が相続するかを決定します。なお、遺産分割協議の決定に際しては、遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が必要です。
必要な書類を準備する
不動産の相続人が決定したら、相続人は必要な書類を集めて相続登記の準備を行いましょう。
相続登記に必要な書類は、被相続人の戸籍関係の書類や相続人に関する書類など多岐に渡ります。
登記申請書は、法務局のホームページでダウンロードできます。法定相続情報証明制度を利用すれば、その写しが他の相続手続きなどにも利用できて便利です。
必要な書類の種類については後述します。
法務局で申請を行う
相続登記の書類が準備できれば、対象の不動産の住所地を管轄する法務局で、必要書類を全て提出して申請します。
登記申請には登録免許税の納付が必要です。窓口で必要な金額の収入印紙を購入し申請書に貼り付けておきましょう。
法務局での審査と登記には、10日前後かかります。登記が済めば、登記識別情報の通知と登記完了証が郵送されるので大切に保管しましょう。
下記の記事では、「【法務局での相続手続き】相続登記の申請方法や注意点」について詳しく解説しています。
こちらの記事も併せて読んでみてくださいね。
相続登記の方法とは
相続登記に限らず、不動産の登記方法は
・単独登記
・共有登記
の2つがあります。
ここではそれぞれについて解説します。
単独登記
被相続人の不動産を1人の人が相続する場合は単独登記と呼びます。
相続人が1人の場合は、土地を担保に融資を受けたり、売却したりするときなどの判断も1人でできるため手続きもスムーズです。
共有登記
複数人で不動産を相続する場合は共有登記となります。
共有登記では、それぞれの所有割合を明記して登記します。
不動産を共有する場合は、次の相続が起こったときに相続人が増えて複雑になりがちです。
不動産活用や売却時には所有者全員の合意が必要であるため、各手続きに手間がかかる可能性があります。
相続登記の必要書類とは
先にも少し触れましたが、相続登記では多種多様な書類を準備しなければなりません。
ここでは手続きに必要な書類について解説します。
登記申請書
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードすると便利です。
事前に取得し、記載例を参考に記入しましょう。
遺言書もしくは遺産分割協議書
相続登記では、遺言書または遺産分割協議書が必要です。
遺言書については、公正証書遺言書の場合は現物のみ、自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所の検認証明書が必要です。
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書は、遺言書情報証明書を添えて提出します。
登記事項証明書
相続した不動産の登記事項証明書も必要な書類です。
以前は、登記簿謄本といわれていましたが、現在は登記事項証明書となっています。
相続対象不動産を管轄している法務局にオンラインで申し込みできます。
住民票と戸籍謄本
相続登記の際には、相続人全員の住民票と戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
法定相続情報証明制度を利用する場合には、相続人全員の住民票が必要となる場合があります。
印鑑証明書
遺産分割協議書には、相続人全員の承諾と署名、実印の押印が必要です。
遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明するためには、相続人全員の印鑑証明書を用意しなければいけません。
印鑑証明は、役所やコンビニなどで取得できます。
固定資産評価証明書
登録免許税を計算するためには、固定資産評価証明書が必要です。
登録免許税の税率は、不動産を取得した方法によって異なりますが、相続による場合は、土地と建物ともに、固定資産税評価額の0.4%と定められています。
被相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍関係の書類では、被相続人の出生から死亡時までの戸籍全部事項証明書が必要です。
役所で取得できますが、遠方の場合は郵送で取り寄せられます。
戸籍が改正されている被相続人の場合は、改製原戸籍謄本・戸籍全部事項証明書が必要になります。
被相続人の住民票の除票
被相続人の住民票の除票は、被相続人が亡くなったこと証明するためのものであり、被相続人の最後の住所地の役所で取得します。
相続登記に必要な費用の目安とは
相続登記には、必ず必要となる費用と削減可能な費用があります。
ここでは、それぞれについて解説します。
登録免許税(必ず必要になる費用)
相続登記で必ず必要となる費用は、登録免許税や各証明書類の取得費用です。
登録免許税の税率については、不動産の取得方法によって異なりますが、相続により取得した場合は、固定資産評価額の0.4%と定められています。
登録免許税は、必要な金額の収入印紙を購入し、登記申請書に添付して提出することで納税とみなされます。
司法書士への報酬(削減できる費用)
司法書士への報酬などは、削減できる費用です。
相続人自身が、相続登記をすれば発生しない費用でありますが、司法書士に相続登記を依頼することにより手続きがスムーズに進みます。
司法書士の報酬の費用相場は、6万円~10万円程度です。しかし、不動産の所在地が遠方だったり、複数の不動産を相続したりした場合は、費用がかさみます。
確実に手続きするには専門家への相談がおすすめ
相続登記は、しっかり準備をして法務局で手続きすれば、相続人自身でも行えます。
しかし、相続に伴うさまざまな手続きを全て相続人が行うことは、多大な時間と労力を要し、大きな負担となるでしょう。
税理士や司法書士などに依頼したり、相談したりすることによって、負担が大きく軽減されます。
相続登記などで、2度手間3度手間にならないように、専門家に相談することがおすすめです。
まとめ
相続登記は、法律により定められていますが、現時点では相続登記をしなくても罰則はありません。
令和6年4月からは、法改正により相続登記の義務化が予定されており、罰則規定も定められました。(令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。)
相続した不動産の相続登記を済ませておかないと、さまざまなデメリットがあるため、相続後は早急に相続登記を済ませましょう。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続の場合は、相続税を始めとして複雑な手続きが多いため、税理士事務所が相続に関する一切を代行するケースも増えています。
また、相続財産が決して多いというわけでなくても、相続トラブルが発生しがちであることにも留意しなければなりません。
できればトラブルが起こる前、生前にできるだけの対策をしておくことが、後々のトラブルを防止する鍵となるでしょう。
相続トラブルを防ぐためには、税理士への相続対策相談がおすすめです。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。