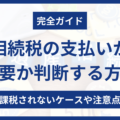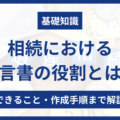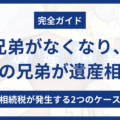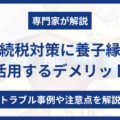相続の手続きにはさまざまな段取りがあり、着実に対応する必要があります。
あらかじめ全体像を確認しておけば、迷わずに手続きしやすくなるでしょう。
この記事では、相続の手続きの流れとともに、対応すべき具体的な内容について解説します。
相続の手続きをスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要です。それぞれ期限が異なるため、漏れなく対応できるように把握しておかなければなりません。
相続手続きには手間や時間がかかりますが、専門家に相談すれば幅広い手続きを代行してもらえます。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
目次
死亡後、7日以内に必要な相続手続き一覧
臨終~葬式
病院で亡くなった場合は、医師が死亡を確認した後に遺体が霊安室へ運ばれます。
病院以外で亡くなった場合は、お悲しみはお察しいたしますが、冷静に落ち着いて、救急車または医師を呼んでください。
事故死や突然死であれば、警察にも連絡が必要です。死亡確認後、医師に死亡診断書を作成してもらいます。
その後、葬儀社を決めて葬式の準備を始めます。
死亡届を提出する
医師から死亡診断書を受け取ったら、市区町村役場へ死亡届を提出します。
死亡診断書と死亡届は用紙がセットになっています。
そして、同時に火葬許可申請書を提出する必要があります。
火葬を行うには火葬許可証が必要であるため、忘れずに手続きをしてください。
年金の受給停止手続きを行う
年金事務所に年金受給権者死亡届を提出し、年金の受給停止の手続きを行います。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている(マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている)場合、手続きは原則不要です。
まだ受け取っていない年金がある場合は、同時に未支給年金を請求するための手続きもする必要があります。
期限は10日(国民年金は14日)以内です。
死亡後、14日以内に必要な相続手続き一覧
世帯主変更届を提出する
亡くなった人と同じ世帯で暮らしている人が2人以上いる場合は、世帯主変更届の提出が必要です。
ただし、残されたご家族が1人である場合など新しい世帯主が明らかであれば提出する必要はありません。
世帯主変更届は、亡くなった人の住所がある市区町村役場の窓口へ提出しましょう。
健康保険に関する手続きを行う
亡くなった人が勤務先で健康保険に加入していた場合は、会社に連絡をとって健康保険証を返却します。
国民健康保険に加入していた場合は、住所地の市区町村役場の窓口で健康保険の資格喪失の手続きをして健康保険証を返却します。
介護保険資格の喪失届を提出する
亡くなった人が65歳以上または40~64歳で要介護認定を受けていた場合は、介護保険資格の喪失届を提出します。
同時に介護保険被保険者証も返却する必要があり、住所地の市区町村役場の窓口に提出します。
公共料金などを名義変更・解約する
公共料金の名義についても変更の手続きが必要です。
今後使用しない場合は解約手続きをしましょう。
早めに手続きをすれば、余計な出費を最低限に抑えられます。
主な公共料金などとしては、電気、ガス、水道、クレジットカード、携帯電話などがあります。
死亡後、3カ月以内に必要な相続手続き一覧
遺言書の有無を確認する
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などの種類があります。
種類によって扱い方が異なるため、よく確認しましょう。
たとえば、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。
検認の請求の場合、申立書を裁判所のホームページからダウンロードすることができ、検認手続き後、検認済証明書を発行できます。
また、自筆証書遺言は、保管制度もあります。
相続人を調査する
相続人調査は、誰が法定相続人にあたるのか明らかにするための重要な調査です。
相続人調査の結果は基礎控除や生命保険金の非課税限度額などにも影響するため、正確な状況を把握する必要があります。
相続の手続きのなかでも特に重要なものであり、慎重に対応しなければなりません。
相続人調査は、亡くなった人の戸籍謄本などの書類をもとに行います。
亡くなった人と関係のある人を洗い出す必要があるため、亡くなった人の出生時から死亡時までの戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍謄本を用意しましょう。
戸籍謄本などを取得するためには、本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。
相続人の優先順位は法律で決まっており、相続人調査の結果をもとに財産を分割して相続します。
相続人調査を確実に進めるためには、専門家に依頼すると安心です。
相続財産を調査する
相続できる財産としてどのようなものがあるかについても確認する必要があります。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産がある場合もあるため、相続を開始する前に実際の状況を明らかにすることが大切です。
それぞれの財産の内容を詳しく調べましょう。
財産調査の始め方として、通帳、郵便物、遺品などを整理することから始めたらいかがでしょうか。
プラスの財産としては、たとえば預貯金や不動産などがあります。
マイナスの財産は、ローン、買掛金、未払債務などです。
なお、中には相続財産とみなされないものもあります。
具体的には、祭祀財産などが該当します。
相続放棄する人がいるか確認する
相続放棄とは、すべての財産を相続しないことです。
マイナスの財産が大きい場合、相続放棄を選択するべきか検討が必要です。
相続放棄は、本人が相続人であることを知ってから3カ月以内に手続きが必要です。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。
なお、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認という方法もあります。
ただし、限定承認は相続人全員が共同で行わなければならず、手続きも煩雑です。
マイナスの財産があっても相続放棄しなくて済むメリットもありますが、慎重に検討しましょう。
死亡後、4カ月以内に必要な相続手続き一覧
所得税の準確定申告を行う
準確定申告とは、亡くなった人の収入について確定申告することです。
亡くなった人が不動産を賃貸していたり、2,000万円を超える給与収入を得ていたりする場合に必要です。
準確定申告は、相続人や包括受遺者などが亡くなった人の生前の住所地を管轄する税務署に提出します。
死亡後、10カ月以内に必要な相続手続き一覧
遺産分割協議書を作成する
相続財産の調査が終わり、遺言書がない場合に遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議とは、相続人が全員集まり、相続した財産をどのように分けるのか話し合うことです。
遺産分割協議を経て決定した内容をまとめた書類が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を作成するには、相続人の実印による押印と印鑑証明書が必要になります。
必ず相続人全員分がそろうようにしましょう。
口座・有価証券などの名義変更・解約手続きを行う
預金口座の名義変更や解約手続きは、銀行で行えます。
亡くなった人が有価証券を保有していた場合は、有価証券についても手続きが必要です。
有価証券の名義変更などは、証券会社の窓口で行いましょう。
また、証券会社によっては、ネットで手続きが可能な場合もありますので、問い合わせをしてください。
不動産の名義変更を行う
不動産を相続する場合は、不動産の所在地を管轄している法務局で名義変更の手続きが必要です。
不動産の名義変更を行う際は、登録免許税がかかります。登録免許税は、不動産の評価額の0.4%です。
なお、必要な書類を事前にそろえておく必要があるため、早めに準備を整えて手続きしましょう。
各財産の名義変更を行う
相続する財産については、それぞれ名義変更を行いましょう。
たとえば、ゴルフ会員権、電話加入権、保険などさまざまな財産があり、自分が相続するものについては漏れなく名義変更を済ませる必要があります。
企業やサービスによって変更方法や必要書類が異なるため、よく確認しましょう。
また、亡くなった人が所有していた自動車やバイクを引き継ぐ場合も、それぞれ名義変更が必要です。
相続税の申告・納税をすませる
相続が発生したときは相続税の申告が必要な場合があります。
基礎控除として定められている「3,000万円+法定相続人の数×600万円」を超える場合は、被相続人が亡くなられた日から10カ月以内に忘れずに相続税の申告と納税を済ませましょう。
まずは亡くなった人の財産を調査し、その財産の評価額を算出し、相続税の総額がいくらになるか計算します。
そのうえで、申告書を作成して納税してください。
相続税の申告や納税を怠るとペナルティの対象になるため、要注意です。
たとえば、正当な理由がないにもかかわらず期限内に相続税の申告をしなかった場合、無申告加算税が課されます。
期限が過ぎた後に自ら申し出れば、無申告加算税は本来の納税額の5%です。
税務調査で発覚すると本来の納税額の15%の無申告加算税が課されます。
相続手続きの申告後に行う手続きとは
遺留分侵害額を請求する
遺留分侵害額請求は、相続分について納得できない場合に認められる手続きです。
遺留分を有するのは、配偶者、子、直系尊属です。
ただし、請求できるのは相続の開始と遺留分の侵害を把握してから1年以内です。
必要があれば、早めに準備して手続きしましょう。
埋葬料・葬祭費を請求する
葬儀にかかる費用の負担を減らすための制度があり、請求すると給付を受けられます。
亡くなった人が健康保険組合に加入していた場合は埋葬料、国民健康保険に加入していたり後期高齢者医療制度の適用を受けていたりした場合は葬祭費を受け取れます。
請求の期限は死亡から2年以内です。
高額療養費の還付を請求する
高額療養費制度は、医療費が一定額以上かかった場合にその分の金額が払い戻される制度です。
本人が死亡した後でも請求できます。
申請書とともに、亡くなった人との関係を証明する書類や医療費の領収書を提出しましょう。
また、亡くなられた方の高額医療費の還付金は相続財産となりますので、ご注意ください。
生命保険金を請求する
亡くなった人が生命保険に加入していて自分が受取人になっていれば、請求が必要です。
受取人が請求しないと保険金は受け取れません。請求期限は死亡から3年以内です。
遺族年金を請求する
配偶者や未成年者の親が死亡した場合は、請求により遺族年金を受け取れます。
自動的に支給されるわけではないため、注意しましょう。
遺族年金の請求ができるのは死亡から5年間です。
相続手続きを専門家に依頼する場合
相続手続きは専門家に依頼するケースも多いです。
相続手続きは複雑であるため、専門家に依頼すると迷わずスムーズに進められます。
ただし、専門家に依頼すればその分の費用もかかります。
費用も考慮したうえで依頼するかどうか決めましょう。
相談内容によって依頼先が異なる
相続手続きの代行は内容に応じて依頼しましょう。
士業によって対応できる内容が異なるためです。
どのような状況であり、具体的に何を依頼したいか確認したうえで、どこに依頼するか決める必要があります。
相続について相談できる専門家とは
相続について相談できる専門家は複数います。
ここでは、それぞれの専門家に何を依頼できるか解説します。
行政書士
行政書士は、相続のために必要なさまざまな書類作成を代行できます。
たとえば、遺産分割協議書の作成を依頼したい場合など、ピンポイントで作業してもらいたいときに相談しましょう。
書類の作成のみを依頼するため、費用を抑えられます。
税理士
税理士は税の専門家であり、相続税の申告について相談できます。
ただし、不動産の名義変更や家庭裁判所の手続きなどには対応できないため、税以外の手続きを依頼したい場合は他の専門家にも相談が必要です。
司法書士
相続財産のなかに不動産がある場合、司法書士に相談して名義変更などを行います。
遺産承継業務にも対応しているため、煩雑な手続きをまとめて代行してもらえます。
弁護士
弁護士は法律の専門家です。相続の分割で揉めた場合に弁護士に相談すれば、法律に基づいて解決してもらえます。
必要があれば、司法書士や税理士とも連携してくれます。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要です。それぞれ期限が異なるため、漏れなく対応できるように把握しておかなければなりません。
相続手続きには手間や時間がかかりますが、専門家に相談すれば幅広い手続きを代行してもらえます。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。