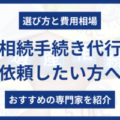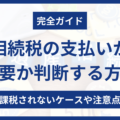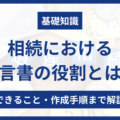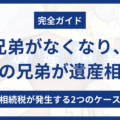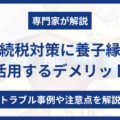自分に相続が発生したとき、今後発生しそうなため相続税に備えておきたいですよね。
その際に、「どのくらい相続税が発生するのか知りたい」と考える人も多いでしょう。
相続税の計算に関しては、税理士に相談することが確実ですが、自分で相続税の計算ができるに越したことはありません。
この記事では、「自分で相続税を計算する方法」について解説します。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続税を自分で計算するためには、まず相続税の課税対象となる財産を正しく評価しなければなりません。
種類によっては控除が必要なものもあります。
そこから、手順に添って計算していくのですが、その計算工程も複数あり手間がかかります。
節税対策を行いつつ正しく相続税を算出するためには、専門家である税理士法人Accompanyにお問い合わせください。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
目次
そもそも相続税の計算は自分でできる?
相続税は、相続を受けた人が支払わなければならない税金です。
相続税の正確な計算が不要で、目安でよい場合は、自分でも相続税は計算可能です。
ここからは、相続税の概算を算出する方法や手順を解説します。
ただし、厳密に計算するためには専門的な知識が必要であるため、正しい結果を出したいときは専門家に相談することをおすすめします。
相続税とは
相続は配偶者、親、子、兄弟姉妹などの親族、また遺言などで自分を相続人として指定した人が亡くなったときに発生します。
相続が発生すると、相続した財産の額に応じて相続税を支払うことになる可能性があります。
ただし相続する財産には相続税が発生するものと発生しないものがあり、必ずしも相続税が発生するとは限りません。
また、財産の金額が定められた金額を越えなかった場合は相続を申告しなくても済み、相続税を支払わなくてもよい場合もあります。
そのため、まずは相続税の申告が必要かどうかを判断しましょう。
相続した財産全てが課税対象ではない
相続税がかかる財産は以下のとおりです。
| 相続や遺贈によって取得した財産 |
・現金 ・預貯金 ・有価証券 ・宝石 ・土地 ・家屋 ・貸付金 など金銭として見積もることができるものすべて |
| 相続財産としてみなされる もの |
・死亡退職金 ・生命保険の死亡保険金 ・生前贈与されていて贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、 非上場会社の株式、事業用資産等 ・一括贈与された教育資金、子育て資金などにかかる 贈与税の非課税を受けたときの管理残額 (教育資金の場合受贈者が23歳未満であるときなどを除く) ・死亡前3年以内に亡くなってから財産の贈与を受けているとき など |
※遺贈とは、遺言書を作成することで、亡くなった人の財産を、法定相続人以外の人に渡す方法のことです。
※法定相続人とは、亡くなった人の遺産を受け取る権利をもつ人のことです。配偶者や子若しくは孫は、常に相続人となります。子や孫がいない場合は両親などに相続人としての権利が移行し、子や孫、両親がいない場合は兄弟・姉妹に相続権が移ります。
反対に相続税がかからない財産は次のものです。
・墓、仏壇など
・宗教や慈善、学術など公益目的の事業を行う一定の個人からの財産で、同じく公益目的で使用するもの
・心身に障害がある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度により支給される給付金を受ける権利(地方公共団体の条例により)
・生命保険金や退職手当金からの相続は、500万円に法定相続人の数をかけた部分
…など
相続財産の総額が一定金額(基礎控除額)を超えるか超えないかが相続税の申告有無に影響する
相続税には基礎控除があり、その分を差し引いた額(課税遺産総額)に相続税がかかります。
つまり、相続財産が基礎控除額に達しないときには、相続税は発生しません。
相続税が発生しないことから、申告や手続きなども不要です。
基礎控除額は法定相続人の数に応じて決められるため人によって異なります。
そのため、まずは基礎控除額がいくらか計算し、課税遺産総額があるかどうか確認しましょう。
次は、相続税の申告が必要になるかどうか判断する方法について解説します。
相続税の申告が必要かどうか判断する方法
相続税の申告が必要になるケースは、相続税が必要となる財産の合計額から基礎控除額を差引き、プラスになった場合です。
そこでマイナスになったときには、相続税が発生しないため税務署への申告は必要ありません。
基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円です。
法定相続人とは、民法で決められた相続を受ける権利を持つ人のことで、相続を放棄した人も含まれます。
養子も法定相続人に含まれますが、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までという制限があります。
ちなみに、血がつながっていない配偶者の子は実子とみなされるため、このような制限はありません。
国税庁の「相続税の申告要否の簡易判定シート」を活用する
上記の計算は自分でもできますが、国税庁のホームページにある「相続税の申告要否判定コーナー」を利用すると、自動で相続税の申告が必要かどうか判定できます。
当該ページにアクセスし、遺産総額の概算と法定相続人の人数を入力して利用してください。
正式な相続税の申告ではないため、遺産の総額は概算でも構いません。
相続税の申告が必要になった場合の計算方法
相続税がかかる財産の総額から、基礎控除額を差引いた課税遺産総額がプラスになったときは、相続税がいくらになるのか計算してみましょう。
相続税の計算手順は、
①相続税の総額の計算
②それぞれの相続税額の計算
③それぞれの納付税額の計算
という順で行われます。
①相続税の総額の計算方法
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率=算出税額
各法定相続人の算出税額を合計すると相続税の総額が計算できます。
②それぞれの相続税額の計算方法
相続税の総額×相続した課税価格÷課税価格の総額=それぞれの相続税額
③実際の納付額の計算方法
上記相続税額から各種税額控除を差し引いた額が納付すべき相続税の額です。
※
法定相続分の求め方:相続人の範囲と法定相続分
相続税の税率:相続税の税率
課税価格の計算方法:相続税の計算
各種税額控除の計算方法:相続税の計算
相続税の計算を自分でする場合の手順6ステップ
相続税を計算するための手順をまとめると、次のようになります。
1.財産を評価し相続税がかかる遺産総額を算出
2.遺産総額から基礎控除を差引き、課税遺産総額を算出
3.課税遺産総額を法定相続分で分け、税率をかける
4.上記、相続人分を合計し相続税の総額を計算する
5.そこから実際に相続割合で分け、それぞれの相続税額を算出
6.各種控除を差引く
具体的にどのように計算するのかは後述してあるため、参考にしてください。
相続税の計算を自分でする場合の注意点
ここまでの解説の通り、相続税を計算するまでは多数の手順が必要です。
そのほか、以下のような注意点があります。
・課税対象となる財産が何かわかりにくい
・生前贈与したものでも課税対象となるものがある
・なかにはマイナス計上できる相続財産もある
・法定相続人の数え方は法律で決まっている
・遺産の分け方を法定どおりにしない場合でも相続税の計算方法は法定どおりにする
・税率は超過分が高くなる累進課税で計算が必要
(税率の計算方法は後述します)
・税額軽減制度を利用できる人とできない人がいる
・兄弟姉妹、孫、他人が相続したときには相続税が加算される
・税額軽減制度(小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減など)を利用して0円になったとしても、申告書の提出は必要
(ちなみに配偶者はほとんどのケースで1億6,000万円まで無税になります)
・相続税にはさまざまな控除があり、どれに該当するのか判断するのは難しい
・相続税の申告や納付には、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内にしなくてはならない
このように、相続税の計算にはさまざまな注意点があります。
計算方法が複雑なだけではなく、法定相続人の人数や実際の相続割合はどの程度か、税額軽減制度は利用できるかなど、法律に詳しくないと対応が難しい部分もあります。
納付方法や納付額を間違えないためには、専門家に依頼したほうがよいでしょう。
相続税の速算表と速算表を使った計算例
相続税の税率は超過分だけ該当する税率に当てはめて計算する必要があるため、計算式は複雑になります。
そこで、あらかじめ控除額を計算してある下記の速算表を利用すると便利です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、法定相続分に応ずる取得金額が5億円だとします。
そのとき、1,000万円以下の分は10%、1,000万円超3,000万円以下は15%…と計算するのではなく、速算表を参照し次のように計算しましょう。
5億円×50%-4,200万円=2億800万円
相続税の計算事例
例として遺産総額1億円、法定相続人が3人(配偶者1人、子2人)のケースで子1人にかかる相続税額を計算します。
①相続税の総額の計算
課税遺産総額の算出
1億円-(3,000万円+(600万円×3))=5,200万円
相続税総額の算出
(配偶者)5,200万円×2分の1×20%-200万円=320万円
(子1)5,200万円×4分の1×15%-50万円)=145万円
(子2)5,200万円×4分の1×15%-50万円)=145万円
320万円+145万円+145万円=610万円
②それぞれの相続税額の計算
610万円×4分の1=152万5,000円
③実際の納付額の計算
控除に該当するものがある場合は、ここからさらに差し引かれて実際に相続税額が算出されます。
相続税の計算で困った場合には税務署や専門家に相談
相続税の計算は想像以上に手間がかかると思った人も多いのではないでしょうか。
相続税の計算で何か困ったことがある場合、一般的な内容であれば税務署へ相談すればよいでしょう。
ただ、税制は毎年のように変化があり、正しく節税対策や財産評価をするためには、税の専門家である税理士に相談することが必要です。
ぜひ一度相談してみてください。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続税を自分で計算するためには、まず相続税の課税対象となる財産を正しく評価しなければなりません。
種類によっては控除が必要なものもあります。
そこから、手順に添って計算していくのですが、その計算工程も複数あり手間がかかります。
節税対策を行いつつ正しく相続税を算出するためには、専門家である税理士法人Accompanyにお問い合わせください。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。