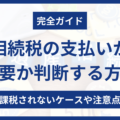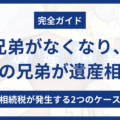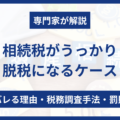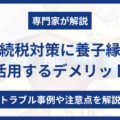相続でもめるのは望ましくないと考えていても、もめるケースは多々あるのが現実です。
この記事では、
・相続でもめる原因
・よく生じるアクシデント(もめごと)にどのようなものがあるか
・もめごとを回避するための解決策
を解説します。
今後の相続に備え知識を得たい人、すでに相続問題を抱えている人などは、知識を持っておくと役立つので、ぜひ参考にしてくださいね。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続には、さまざまなもめごとの要因が付きものです。
また、相続財産が決して多いというわけでなくても、相続トラブルが発生しがちであることにも留意しなければなりません。
できればトラブルが起こる前、生前にできるだけの対策をしておくことが、後々のトラブルを防止する鍵となるでしょう。
相続トラブルを防ぐためには、税理士への相続対策相談がおすすめです。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
目次
相続でもめる原因を理解しておこう
相続においてもめごとになりやすい原因をあらかじめ知っておくことで、ある程度の対策ができます。
以下ではぜひ知っておきたい、相続でもめる原因について解説します。
まず知っておくべきこととして、相続には一次相続と二次相続があります。
一次相続とは、「両親のうち片方が亡くなり、亡くなった人の財産を配偶者と子どもが相続するケース」です。
二次相続は、「この配偶者が亡くなった場合に、一次相続で配偶者が相続していた財産を子どもが相続するケース」です。
本記事では特に一次相続について解説します。
相続の際に生じるもめごと|4つの主な原因
相続でもめごとが生じる原因はさまざまです。
遺産を得るためにもめることもありますが、誰も相続したがらずにもめる場合もあります。
相続人の立場の違いや遺産に対する思い入れの差、相続人同士が不仲・疎遠であることや、遺産の種類などが、もめごとの主な原因です。
ここでは、主な4つの原因について掘り下げて解説します。
なお一次相続でも二次相続でも、もめる原因はほぼ同じです。
ただし、一次相続では亡くなった人の配偶者が仲裁できる可能性がありますが、二次相続の場合は子ども達だけで遺産について話し合います。
そのため、より感情的になって、もめごとがエスカレートしてしまう可能性もあります。
原因1:相続人の立場の違い
もめごとの原因としてまず挙げられるのは、相続人の立場の違いです。
たとえば、被相続人が事業を営んでいた場合、その事業を継ぎたいと考えている人が、土地や建物などの事業基盤を相続したいと主張することがあります。
あるいはほぼ実家しか遺産がないという場合に、長男が「家を継ぐのは自分だ」と主張して、他の兄弟ともめるケースも珍しくありません。
その他に、被相続人から生前にお金の支援を受けていた相続人と受けていなかった相続人、被相続人の介護に関わった相続人と介護していない相続人なども、立場の違いでもめるケースです。
下記の記事では、「【兄弟間の相続】両親が亡くなり、子どもである兄弟にのみ相続が発生するケース」について詳しく解説しています。
該当する方は、こちらの記事も併せて読んでみてくださいね。
原因2:遺産への思い出や思い入れの違い
それぞれの相続人が持っている遺産への思い入れや思い出の違いも、相続トラブルの元になることがあります。
たとえば、実家に関して、相続人のなかに「被相続人との思い出があるから相続したい」あるいは「実家の形をそのまま残したい」と考える人がいます。
一方で、「特に実家には思い出がないのでお金に変えたい」と考える相続人もいるでしょう。
こういったケースでは、実家の扱いをめぐってもめごとになりやすいといえます。
また、被相続人名義の実家で被相続人と同居していた、あるいは現在もなお実家に住んでいる相続人にとっては住む場所がなくなってしまうことから、残してほしいと主張し、もめるケースもあるでしょう。
なお、現在、亡くなった人の配偶者については、その家に住み続けることができる配偶者居住権が認められています。
自宅に関する権利を配偶者居住権と所有権とに分けて相続することで、自宅の所有権を配偶者が相続できなくても住み続けられる可能性が高くなっています。
原因3:相続人同士が不仲・疎遠
もともと相続人同士が不仲だったり、疎遠だったりする場合には、意見が合わずもめるケースは多いといえます。
当事者間で穏便に解決することが難しいこともあるため、必要に応じて仲介を立てる、専門家を入れるなど、大きくこじれる前に対応することをおすすめします。
原因4:遺産の種類
分与しにくい資産が多いケースでは、もめる可能性が高まります。
具体的には、不動産です。
現金化して分けられれば楽ですが、そうでない場合はよく分割方法を検討する必要があるでしょう。
これに対して、金融資産が多い場合は分与しやすいといえます。
【注意】もめごとは相続財産の大小に限らず起こる
「もめるほどの資産はないから安心だ」と考えている人もいますが、相続に関するアクシデント(もめごと)は相続財産の大小に限らず起こり得るので注意が必要です。
司法統計年報のデータによると、2021年(令和3年)に全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事案6,934件のうち、遺産総額5,000万円以下のケースが全体の実に8割近くを占めています。
具体的な相談割合は、以下の表を参照してください。
| 相続遺産の総額 | 全体に対する割合 |
| 1,000万円以下 | 約33%(2,279件) |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 約44%(3,037件) |
| 上記以外 |
約23%(1億円以下864件、5億円以下493件、5億円を超える28件、算定不能・不詳233件→合計1,618件) |
出典:令和3年司法統計年報3家事編|最高裁判所事務総局
「第50表遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―特別受益分考慮の有無別―全家庭裁判所」をもとに加工
このように、遺産総額1,000万円以下であっても、遺産分割事案全体のおよそ3割を占めるほど多いことがわかります。
相続財産となる自分の資産総額が決して大きくないからといって、何も相続対策をとらないと、自分の亡きあとにもめごとが起こるおそれがあります。
配偶者に負担をかけることになったり、子どもたちの間に争いが起こったりする可能性もあるということです。
もめごと対策は早めに行っておくことをおすすめします。
相続があった際によく生じるもめごとの例
次に、相続があった際によく生じるもめごとの例を7つ、それぞれ紹介します。
不動産資産が多くて生じる問題
もめごとの原因でも触れたとおり、土地や建物など不動産資産が多い場合、もめる可能性が高まります。
不動産によって資産価値や将来性が異なるため、誰がどの不動産を取得するかでもめることはよくあることです。
逆に固定資産税や維持費を支払えないなどの理由で誰も取得したがらずもめることもあります。
たとえば、不動産を代償分割するか換価分割するか、不動産の評価方法はどうするかなどでもめるケースは多いでしょう。
また、遺産分割方法が決まらないため相続登記せずに放置したり、共有状態にした結果、活用も売却もできず放置してしまったりすることも起こり得ます。
もしくは一部の相続人が居住しているため売却が難しいケースや、売却しようとしても買い手がつかない場合も珍しくありません。
状況によっては相続人全員で相続放棄する場合もあるでしょう。
親が事業をしていた場合に生じる問題
親が事業をしていた場合、後継者になる相続人とそれ以外の相続人とで意見が合わず対立する可能性があります。
後継者が必要な株式や資産を承継できなければ、経営ができずに会社が廃業に追い込まれる可能性もあるでしょう。
事業は財産内容が複雑なため分割しにくく、また保証債務も相続の対象になるので注意が必要です。
特定の相続人だけに高額の生前贈与があり生じる問題
特定の相続人だけに生前贈与があった場合、被相続人が亡くなったときにもめる可能性があります。
不公平をなくすため、生前贈与を「特別受益」として扱い、相続財産の一部として計算する方法もあります。
しかし、何が特別受益に当たるかの判断が難しいため、特別受益をめぐってさらにもめる場合が少なくありません。
特別受益については、遺産分割協議で加味されるべきものではありますが、年月が経つと特別受益や寄与分に関する記憶や証拠があいまいになってきます。
そのため、遺産分割協議の難航、相続登記の未了を起こす原因になることも多々ありました。
下記の記事では、「【相続登記とは何?】放置した場合のデメリット・必要性」について詳しく解説しています。
こちらの記事も併せて読んでみてくださいね。
特定の相続人が財産管理していて生じる問題
亡くなった親の財産を、生前から特定の相続人が管理しているケースがあります。
たとえば、兄弟のなかで親と同居している人が財産管理をしている場合などです。
この場合、親が亡くなったタイミングで他の兄弟から使い込みや財産隠しを疑われてしまい、もめる可能性があります。
二次相続で多く見られるケースですが、高齢の両親のうち片方が亡くなった場合も、生前から兄弟のうち1人が財産管理をしていれば同じことが起こり得るでしょう。
介護の負担に偏りがあったうえ、寄与分が認められず生じる問題
寄与分とは、亡くなった親の介護をしていた、家業を無給で手伝っていた等の代償として、該当する相続人にのみ認められる相続財産の増額分のことです。
寄与分が認められると特定の相続人だけ相続財産が増えるため、特定の相続人に介護などの負担が偏ると、もめごとは起こりやすくなります。
寄与分として認められるかどうかは特別受益と同様に判断が難しく、寄与分を主張することでもめごとがさらに大きくなる可能性もあります。
なお2019年7月から、民法改正によって特別寄与料の請求制度が創設されました。これは相続人の配偶者が介護などに著しく寄与している場合、相続人本人に介護への寄与がなかったとしても、特別に寄与分が認められる制度です。
特別寄与料を請求できるのは、6親等以内の血族、及び配偶者並びに3親等以内の姻族に限られます。
本来は法定相続人以外に寄与分は認められませんが、この改正をもって、該当する肉親は特別寄与料という形で、相続人に対して自身の特別寄与分を主張できることになりました。
被相続人の死亡時に、家族以外の子どもや内縁の配偶者がいることで生じる問題
被相続人の死亡時、表だった家族以外に相続人がいるともめごとにつながりやすくなります。
たとえば、前妻との間にできて他の第三者と特別養子縁組していない子ども、認知した子ども、内縁の配偶者などがいるケースです。家族として生活していた相続人が知らなかった新たな相続人や、突然現れた想定外の相続人などがいるともめやすくなります。
こうした相手がいることがわかっても連絡がとれない、連絡をしても無視される、連絡がついてもお互いに感情的になってしまうといったケースでは、遺産分割協議が進まないことがあります。
何らかの問題が想定できる場合は後々の争いを回避しやすくするため、自分が亡くなる前に遺言を残しておくことも検討しましょう。
残された遺言書が不公平な内容になっていて生じる問題
被相続人の死亡時に遺言書がある場合、内容が不公平でも書類としては有効です。
ただし、遺言書に納得できない相続人により遺言書無効確認調停や訴訟が起こされたり、「遺留分」を侵害している場合は死後に遺留分侵害額請求が行われたりする可能性があります。
相続でのもめごとを避けるためにはどうしたらいいか
・相続でもめる原因
・よく生じるアクシデント(もめごと)にどのようなものがあるか
について解説してきました。
次に、「相続でのもめごとを避けるためにはどうしたらいいか」について解説します。
生前にできる限り対策しておく
相続によるもめごとを避けるためには、生前にしっかりと財産調査したうえで、遺産内容や管理方法、被相続人の希望や考え方などを家族で話し合っておくことがおすすめです。
認知症の不安がある場合は、後見制度を利用すれば財産管理ができます。
遺言書作成の際は、遺言トラブルにつながらないよう内容面に配慮した遺言書を作成する必要があります。
また、民事信託(家族信託)といって、生前から死後にかけての財産管理方法や死後の財産帰属先等を取り決める方法もあるので、利用を検討しましょう。
死後、遺言が無い場合には遺産分割協議をすることになる
被相続人の遺言がない場合は、相続人たちで遺産分割協議を行います。
協議によってスムーズに財産分与の内容を決められれば、大きな争いは起こりません。
ただし、相続人のなかに行方不明者や認知症の人がいる場合、遺産分割協議ができなくなるため注意が必要です。
相続内容や人間関係が複雑な場合は専門家への相談がおすすめ
上述のように、相続人のなかに行方不明者や認知症の人がいる場合は、家庭裁判所での手続きが必要になります。
また、相続人同士でもめごとが起こり、話し合っても解決しない場合は、家庭裁判所へ持ち込んで民事調停や審判による解決を図らなければなりません。
したがって、遺産に不動産資産が多い場合、相続人が多いなど相続が複雑になりそうな場合、すでに相続でもめているといった場合などは、早めに相続に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
もめごとを回避したい場合、事前対策として「財産調査」や「公正証書作成」を行うことができます。こうした作業は弁護士や司法書士、行政書士に依頼すればスムーズです。
相続について専門家に相談するメリット
専門家に相談すると、相続に関して法律に沿った正しい考え方がわかります。
正確なことがわからずに争ったり、悩んだりするよりもずっと建設的です。
また、第三者の目線で最適な遺産分割提案をしてもらえるため、もめごとが起こってしまったとしても、早期解決できる可能性が高まります。
まとめ
この記事では、
・相続でもめる原因
・よく生じるアクシデント(もめごと)にどのようなものがあるか
・もめごとを回避するための解決策
を解説しました。
今後の相続に備え知識を得たい人、すでに相続問題を抱えている人にとって、この知識が参考になれば幸いです。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続には、さまざまなもめごとの要因が付きものです。
また、相続財産が決して多いというわけでなくても、相続トラブルが発生しがちであることにも留意しなければなりません。
できればトラブルが起こる前、生前にできるだけの対策をしておくことが、後々のトラブルを防止する鍵となるでしょう。
相続トラブルを防ぐためには、税理士への相続対策相談がおすすめです。
税理士法人Accompanyでは、相続税の申告、相続対策についてサービスを提供させて頂いています。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。