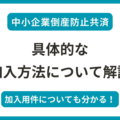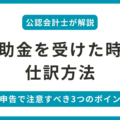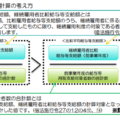繰越欠損金9年を更に延長
今日の日経の記事からです。
政府税制調査会で繰越欠損金の利用期間の制限が現状9年から更に延長する案が出ているそうです。
繰越欠損金とは、決算の時にでる赤字(税金を計算するうえでの)のことです。
繰越欠損金は、決算の時に赤字が出た場合、赤字が出た年以降の黒字と相殺できることとなっています。
繰越欠損金があると、繰越欠損金が昨年の決算時に、100万円出た場合、今年の決算時に黒字が100万円出た場合、昨年の繰越欠損金100万円と今年の黒字100万円を相殺して黒字がなかったことにして税金を計算できます。
現制度では、法人で9年より前に発生した赤字は黒字と相殺できないとなっています。
また、資本金1億円超の企業の繰越欠損金は、現状のその年の黒字の8割までとして利用制限を課しています。
利用割合限度があることにより、資本金1億円以上の企業の税金負担が大きくなってしまうことに対する救済案的に今回の改正案があるようです。
例えば、現状、1億円超の企業の利益が5000万円の場合、繰越欠損金が8000万円あっても、全額利用できません。
5000万円×80%=4000万円…繰越欠損金利用限度
その年の税金 (5000万円-4000万円)×税率35%=350万円となります。
延長案の趣旨は、米英では、欠損金の利用期間が無制限となっていることから、利用期間の制限がある日本は国際競争力の観点から不利であるとの観点からです。
国際的な観点もそうですが、個人的には、欠損金の利用期間の制限も、利用割合限度もおかしい制度だと思います。
なぜなら、欠損金が発生しているという事は、いくら昔であっても、税務上とはいえ赤字を発生させた以上、社外留保がある場合は別ですが、資本金が相当厚くない限り、借入金等が発生し、企業自体の財務は弱まっており、税金を納める能力は低下している可能性は高いからです。
そのような企業の財務内容を加味しない税負担を求めるのはどうかと思います。
それよりも、国には、法人税率の大胆な引き下げをお願いしたいと思います。
様々な節税対策を行い、企業体力を弱め、税金を回避する企業が減り、これにより自己資金を増やしやすい税制にしていただきたいと思います。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。