予定納税が多くて困ったら?減額申請で負担を減らす手続きと注意点
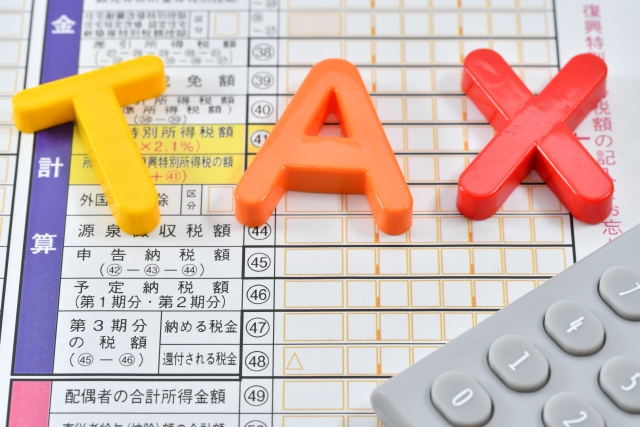

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
毎年6月頃になると、前年の所得に基づいて「予定納税額の通知書」が税務署から届きます。
前年に一定額以上の所得があった方は、翌年3月の確定申告を待たずに、あらかじめ所得税の一部を納める「予定納税」が義務づけられています。
しかし、「今年は経済状況の変化や事業の縮小などにより、所得が前年よりも大きく減少する見込みである」という方もいらっしゃるかと思います。
実は、「今年の所得が減少する見込みがある場合」は、予定納税の減額申請を行うことが可能です。
正当な手続きによって納税額を引き下げたり、納税自体を不要とすることもできます。
この記事では、所得税の予定納税制度の概要から、減額申請の条件や手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
資金繰りの悪化を防ぐためにも、制度を正しく理解し、必要に応じて適切な申請を検討しましょう。
予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得に基づいて、あらかじめ今年分の所得税の一部を納付する制度です。
所得税は本来、毎年1月1日から12月31日までの所得を翌年3月15日までに確定申告して納付するものですが、前年の所得が一定額を超える場合には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付され、今年分の税金の前払いが求められます。
予定納税が必要になる条件
予定納税の対象となるのは、以下の2つの条件を満たす場合です。
- 前年分の確定申告における「所得税額」が15万円以上であること
- 「予定納税の基準額」が15万円以上であること
つまり、源泉徴収されていない自営業者や不動産所得者などが、前年に比較的多くの所得があった場合に該当します。
予定納税の基準額とは
予定納税基準額は、通常は前年の申告納税額がそのまま使われます(原則)。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外的な計算方法が用いられます。
【例外計算の対象となる条件】
前年の所得に以下のような一時的・臨時的な所得(=除外所得)が含まれている場合
- 山林所得、退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(業務外)、平均課税の適用を受けた臨時所得など
※上場株式等の配当など、一定の分離課税所得は除きます - 外国税額控除の適用を受けている場合
- 災害減免法の適用を受けている場合
【例外的な計算方法】
これらに該当する場合は、
「除外所得がなかったもの」として前年分の所得税額を再計算し、
そこから除外所得に対応しない源泉徴収税額を差し引いた上で、
復興特別所得税を加算した合計額が、予定納税基準額となります。
予定納税のスケジュール
予定納税は通常、年2回(第1期・第2期)に分けて納付します。
それぞれの納付期限は次の通りです。
| 区分 | 納期限 | 納付額の目安 |
|---|---|---|
| 第1期分 | 7月31日(土日祝の場合は翌日) | 基準額の1/2 |
| 第2期分 | 11月30日(土日祝の場合は翌日) | 基準額の1/2 |
予定納税は「前払いの所得税」
このように予定納税はあくまで前払いであって、最終的な納税額は翌年の確定申告で精算されます。
もし払いすぎていた場合は、確定申告時に還付されることになります。
しかし、所得が減っている年に過大な納付をすると、一時的に資金繰りが圧迫される可能性もあります。
そこで重要になるのが、次の章で解説する「減額申請」です。
予定納税の減額申請について
所得税の予定納税は、前年の所得をもとに計算されるため、今年の実際の所得が減少している場合でも、多額の納付通知が届くことがあります。
例えば、
- 今年は収入が大幅に減少した
- 事業を廃業したため所得がなくなった
- 自然災害や病気などやむを得ない事情で所得が減った
こうした場合、予定納税のまま納付すると不必要な負担となることがあります。
そこで、実際の所得が前年より減少していると見込まれる場合には、税務署に「予定納税の減額申請」を行うことで、納付額の軽減や免除を受けることが可能です。
減額申請のポイントは下記になります。
- 減額申請は「今年の所得が前年に比べて減少すること」が前提条件です。
- 廃業や休業、病気などのやむを得ない事情も理由として認められます。
- 申請には、減額を希望する理由と見込み所得額を税務署に伝える必要があります。
- 減額が認められれば、納付額が減り、無理のない納税が可能となります。
このように、減額申請は予定納税の負担を適正化し、納税者の事情に応じた対応を可能にする重要な制度です。
予定納税の減額申請の具体的な手続き方法
1. 申請のタイミング
予定納税の減額申請は、期限までに税務署に申請書を提出する必要があります。
第1期分及び第2期分の減額申請
その年の7月1日から7月15日まで
第2期分の減額申請
その年の11月1日から11月15日まで
※どちらも提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
2. 申請書の提出先
所轄の税務署(自宅や事業所の所在地を管轄する税務署)に提出します。
提出方法は以下のいずれかです。
- 税務署窓口に持参
- 郵送
- e-Tax(電子申告システム)による提出
3. 必要書類・内容
申請書には以下の内容を記載します。
- 減額申請の理由(例:収入減少、廃業、病気等)
- 今年の所得の見込み額や収入の状況
- 申請者の氏名・住所・連絡先など
4. 税務署の審査・通知
申請書が提出されると、税務署が内容を審査し、認められれば減額後の予定納税額が決定されます。
結果は申請者に通知されます。
5. 減額後の納付
認められた減額後の予定納税額に基づき、納付を行います。
減額が認められなかった場合でも、確定申告時に最終的な税額が調整されるため、過納分は還付されます。
減額申請書の提出や必要事項の記載方法の詳細については、国税庁「予定納税の減額申請手続」のページを参考にしてください。
予定納税の減額申請でよくある注意点・ポイント
- 申請理由は具体的に
減額申請が認められるかは、理由の妥当性や根拠資料の有無が重要です。
収入減少の状況や廃業などの事情をできるだけ具体的に説明しましょう。
- 申請はお早めに
期限を過ぎると減額申請が認められなくなるため、できるだけ早めに手続きを行うことが大切です。
- 計算の根拠がわかる資料を準備しましょう
減額申請をするときの計算の基礎となった資料の添付が求められるので、
6月までの所得の状況がわかる資料や廃業届・休業証明、診断書など、
所得が減少した事実を裏付ける書類を準備しましょう。
これらのポイントを押さえることで、予定納税の減額申請をスムーズかつ確実に進めることができます。
申請が認められなかった場合の対応
予定納税の減額申請を税務署が認めなかった場合でも、慌てる必要はありません。以下のポイントを押さえて対応しましょう。
1. 確定申告での精算
予定納税はあくまで前払いの性格を持つため、確定申告時に実際の所得と税額が確定します。
申請が認められなくても、最終的な納税額との差額は確定申告で還付または追加納付により調整されます。
2. 資金繰りの検討
予定納税額が多額で資金繰りが厳しい場合は、税務署に相談し、納付猶予や分割納付の申請を検討しましょう。
これにより、一時的な資金負担を軽減できます。
3. 次回以降の対応策
翌年度以降も同様の問題が生じる場合は、事前に収入予測を正確に行い、早めに減額申請や税務署への相談を行うことが重要です。
予定納税の減額申請が認められなかった場合でも、確定申告での調整があるため過払いにはならず安心ですが、資金繰りの問題には注意が必要です。
まとめ
所得税の予定納税は、前年の所得をもとに算出されるため、今年の実際の所得が減少している場合でも、多額の納付が求められることがあります。
このような場合、納税者にとっては資金繰りの負担が大きくなり、経済的な影響が懸念されます。
そこで、実際の所得が前年に比べて減少する見込みがある場合は、税務署に「予定納税の減額申請」を行うことが可能です。
減額申請を適切に活用することで、過剰な納付を回避し、負担の軽減を図ることができます。
申請には期限があり、申請理由や見込み所得を具体的に説明する必要があるため、早めの準備と対応が重要です。
万が一申請が認められなかった場合でも、確定申告での精算により過納分は還付されますが、資金繰りの観点からは早期の対策が望ましいです。
予定納税の減額申請や資金繰り、その他経営についてお困りのことなどがあれば、ぜひ弊社へお問い合わせください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
弊社では、「キャッシュが増えていない理由、キャッシュが増えている理由」についてご相談を、初回無料で承っております。
決算書を2期分ご準備いただければ、100%明確にすることが可能です!
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
キャッシュを増加させるためのシミュレーションも可能です。ぜひお問い合わせください。
\24時間365日受付中 /

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。
